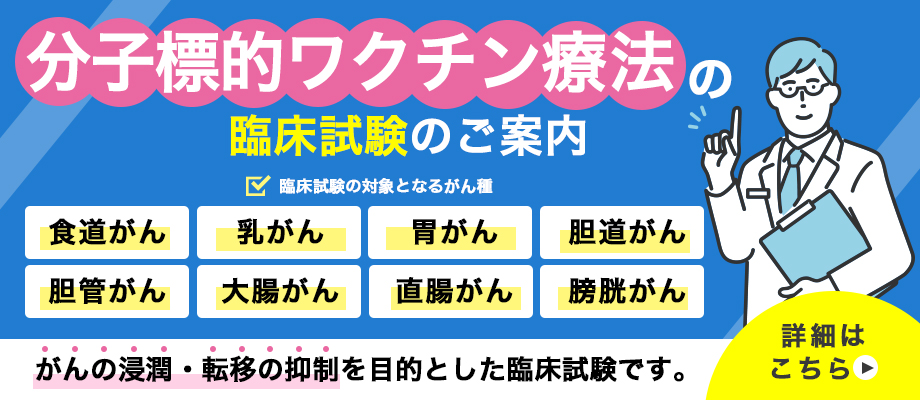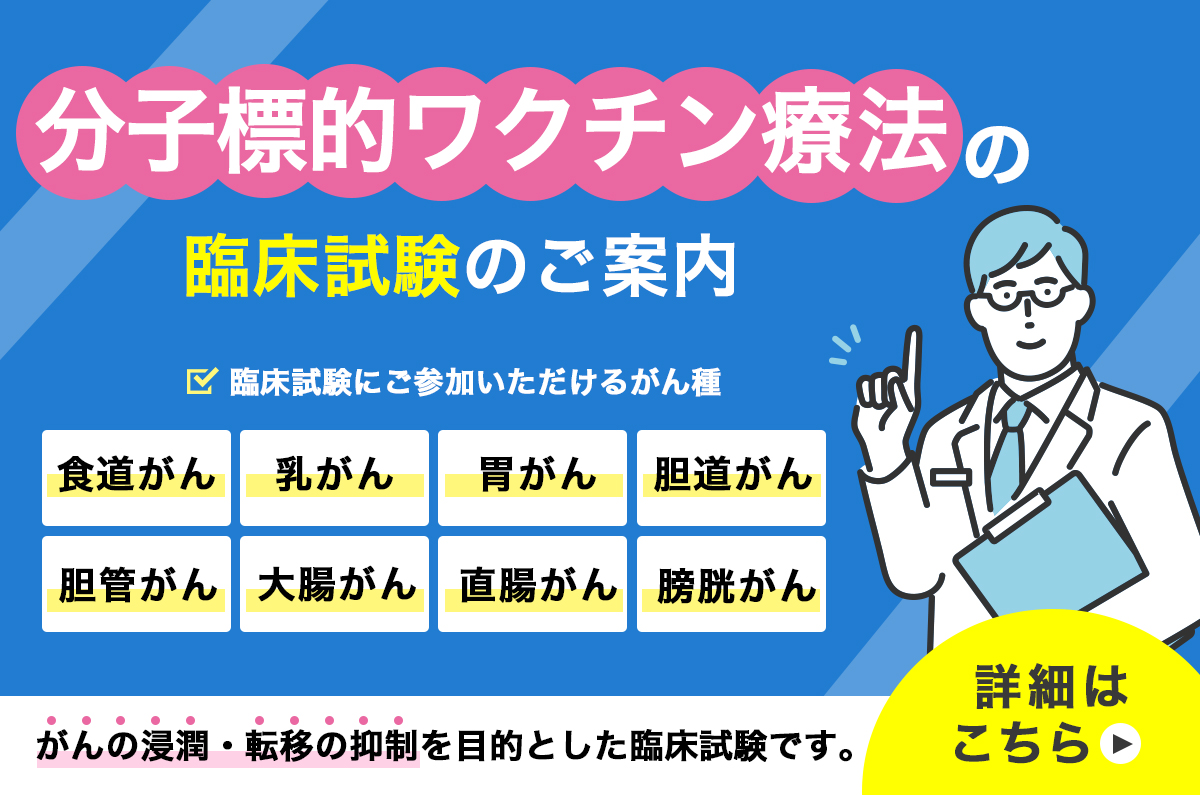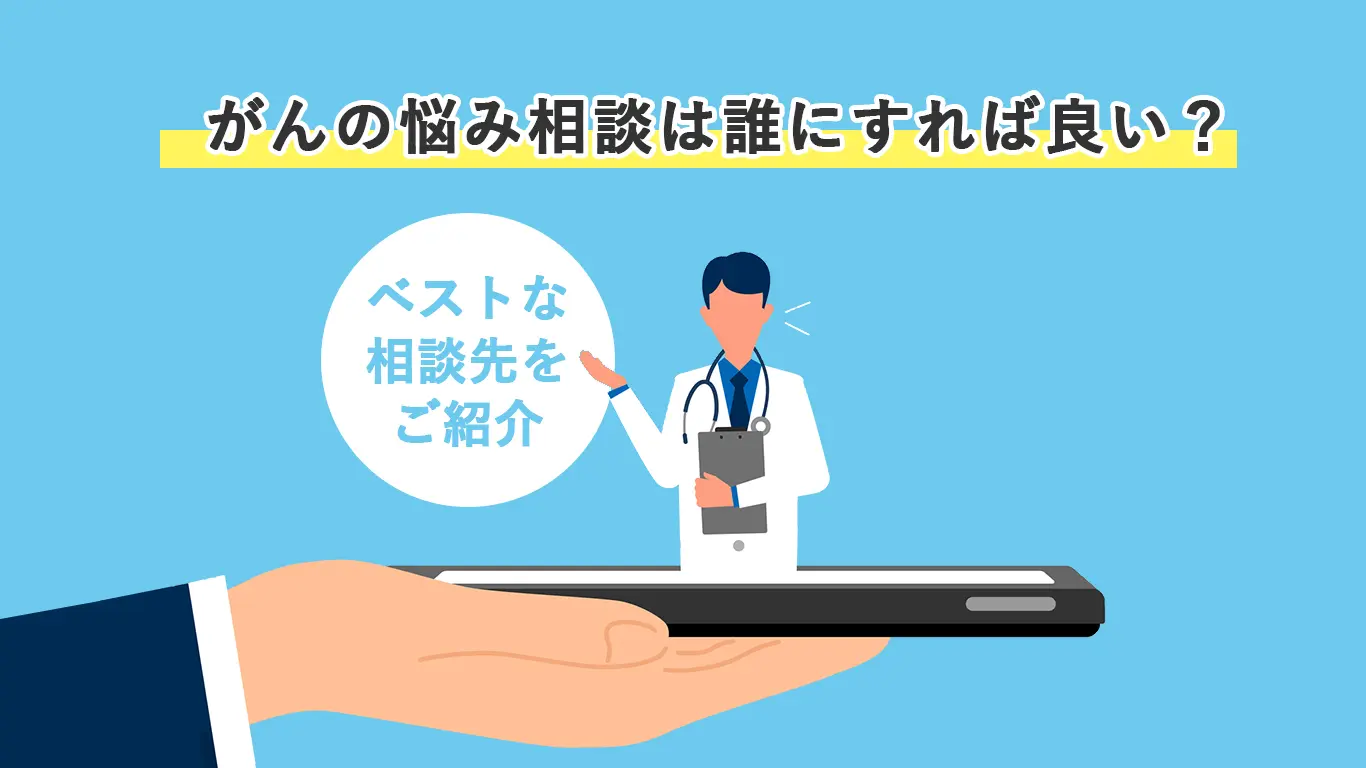抗がん剤は多くのがん治療で用いられる重要な方法ですが、全ての患者さんに効果があるとは限りません。中には、治療を継続しても十分な効果が得られず、不安を抱える方もいらっしゃいます。
本記事では、抗がん剤が効かない場合に考えられる原因や、検討可能な治療法についてわかりやすく解説します。
目次
抗がん剤が効かないときのサイン
抗がん剤の効果は、画像検査や血液検査に加え、症状の変化からも判断されます。
以下に、抗がん剤が「効いているサイン」と「効いていないサイン」をまとめました。
| 項目 | 効いているサイン | 効いていないサイン |
|---|---|---|
| 腫瘍の変化 | 腫瘍が縮小している | 腫瘍が縮小せず、増大している |
| 転移の状態 | 新しい転移が見られない | 新たな転移が確認される |
| 症状の変化 | 痛みや倦怠感が軽減する | 症状が改善せず悪化する |
| 副作用とのバランス | 副作用があっても症状改善がある | 副作用だけ強く、症状改善がない |
これらは一例であり、状態は個々によって異なります。気になる症状があるときは、自己判断せず主治医に相談することが大切です。
なぜ抗がん剤が効かなくなるのか

抗がん剤は初期に効果を示しても、時間の経過とともに効きにくくなる場合があります。その大きな要因のひとつが「薬剤耐性(AMR:Antimicrobial Resistance)」 です。
がん細胞は遺伝子変異によって薬の作用を逃れたり、薬を細胞外に排出したり、自身のDNAを修復する力を高めることで生き残ろうとします。
また、がんの種類によっても効果には個人差があり、例えば膵臓がんや胆管がん などは抗がん剤が効きにくいとされています。特に卵巣がんは初回治療には高い効果を示しますが、再発後は抗がん剤の効果が初回より短いことが知られています 。
抗がん剤が効かなくなった時の続ける・やめる判断
抗がん剤の効果が弱まったとき、治療の継続と切り替えは大きな分岐点となります。状況に応じた判断に加えて、セカンドオピニオンや臨床試験・治験の検討も重要です。
抗がん剤を続けた方が良い場合
抗がん剤は腫瘍を完全に消すことが難しくても、増大を抑えて病状の進行を遅らせる効果が得られる場合があります。このように「一定の効果が維持されている」と判断できるときは、治療を継続することが選択肢となります。また、副作用が強くても、投与量の調整や薬の併用によって症状を和らげ、QOL(生活の質)を保ちながら治療を継続できる場合もあります。
治療をやめる/切り替える場合
抗がん剤による副作用が強く、日常生活に大きな支障をきたしている場合、治療を無理に継続することがかえって負担がかかることがあります。その際は、余命を考慮し、延命を優先するのではなく、痛みや不安を和らげる緩和ケアに切り替えることも重要な選択肢のひとつです。抗がん剤治療をやめることは「諦める」ことではなく、自分らしい生活を取り戻すための前向きな判断といえます。
セカンドオピニオン・臨床試験の参加という選択肢
抗がん剤が効きにくい場合、主治医以外の専門医から意見を聞く「セカンドオピニオン」を受けることで、新しい治療法や方針が見つかることがあります。また、最新の薬や治療法を試す方法として、臨床試験や治験への参加を検討することも可能です。ただし、これらは募集期間が限られている場合が多いため、早めに情報を集め、行動することが求められます。
抗がん剤が効かないときの次の治療

抗がん剤が効かない場合、別の治療法を検討するという選択肢があります。ここでは、患者さんの病状や体調を踏まえた次の治療法について、ご紹介します。
分子標的治療・免疫チェックポイント阻害薬
分子標的治療 は、がん細胞の増殖に関わる特定の分子を狙って作用する薬で、EGFR(上皮細胞増殖因子受容体) 阻害薬などが代表的です。また、免疫チェックポイント阻害薬は、がんに抑え込まれた免疫機能を回復させる薬で、PD-1(Programmed Cell Death 1)阻害薬などが広く用いられています。
これらは従来の抗がん剤が効かない場合でも効果を示す可能性があり、副作用の内容も異なるため、新たな治療の選択肢として注目されています。
メトロノミック療法(低用量・頻回投与)
メトロノミック療法は、抗がん剤を通常よりも低用量で、間隔を空けずに繰り返し投与する方法です。腫瘍を直接小さくするのではなく、がん細胞に栄養を送る血管の新生を抑えることで、進行を防ぐ仕組みとされています。
高齢者や体力が低下している患者さんでも実施しやすく、副作用を軽減しながら腫瘍の増殖を抑える点が特徴です。
抗体薬物複合体(ADC)など精密医療
抗体薬物複合体(ADC:Antibody-drug conjugate) は、がん細胞を狙う抗体に抗がん剤を結合させ、薬を効率的に届ける治療法です。
正常な細胞への影響を抑えながら効果を期待できる点が利点とされます。現在は一部のがん種で承認されていますが、臨床試験や保険外診療での導入も進んでおり、今後の適応拡大が見込まれる先端的な医療のひとつです。
免疫細胞治療(CAR-T療法・樹状細胞ワクチンなど)
免疫細胞治療は、患者さん自身の免疫細胞を利用してがんを攻撃する方法です。代表的なものとして、遺伝子改変させたリンパ球を用いるCAR-T(Chimeric antigen receptor-T cell、キメラ抗原受容体遺伝子改変T細胞)療法 や、免疫を高める樹状細胞(DC:Dendritic cell)ワクチン があります。
再発や難治性のがんで検討されることが多い一方、国内では保険適用外のケースが多く、自由診療や臨床試験を通じて受けられるのが一般的です。
抗がん剤は何年続けられるのか?副作用と向き合う工夫

抗がん剤をどのくらいの期間続けられるかは、患者さんの状況によって大きく異なります。がんの種類や進行度、体力、そして副作用への耐性などが関わるため、明確な年数を一概に示すことはできません。
長期にわたって投与が可能な場合もありますが、副作用によって認知機能の低下や心臓・腎臓などの臓器障害が起こるリスクも指摘されています。そのため、定期的な検査で体調を確認し、必要に応じて投与量の調整や休薬を行うことが重要です。
抗がん剤が効かないときの生活面・心のケア
抗がん剤の効果がはっきりと見えない時期は、先の見通しが立たず、不安やストレスで心身に大きな負担がかかることがあります。そんなときは、消化の良い栄養価の高い食事を意識し、無理のない範囲で散歩や軽い体操を取り入れることが大切です。
また、気持ちの落ち込みや不安を一人で抱え込む必要はありません。がん相談支援センターや患者会といった支援団体、医師や看護師に相談することで、具体的な対策や心のケアを得られます。
「治療」だけでなく、「生活」と「心」を整える工夫が、次の治療に前向きに取り組む力となります。
抗がん剤が効かないと感じたら専門家に相談を
抗がん剤が効いていないように感じても、その理由は薬剤耐性や体調、がんの種類などさまざまで、一概に「治療の終わり」を意味するものではありません。
自己判断で治療を中断するのは避け、まずは主治医に率直に気持ちを伝えることが大切です。
さらに、がん相談支援センターなどの公的窓口を利用すれば、専門家から客観的な意見や新しい治療の選択肢について情報を得られます。不安を一人で抱え込まず、相談することが次の一歩につながります。