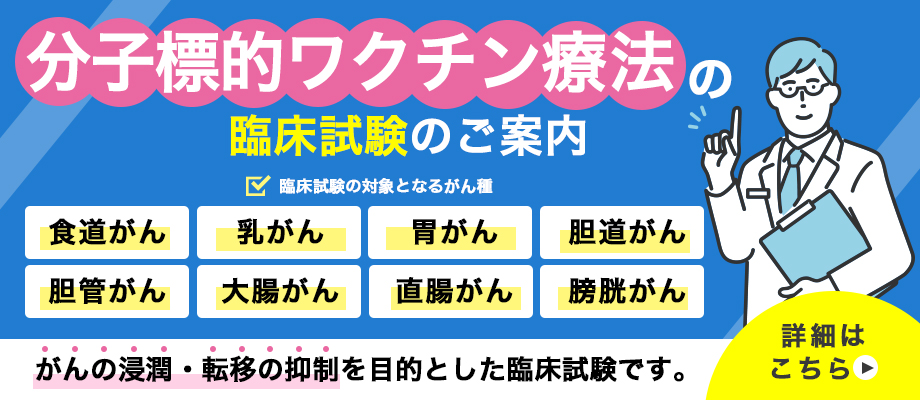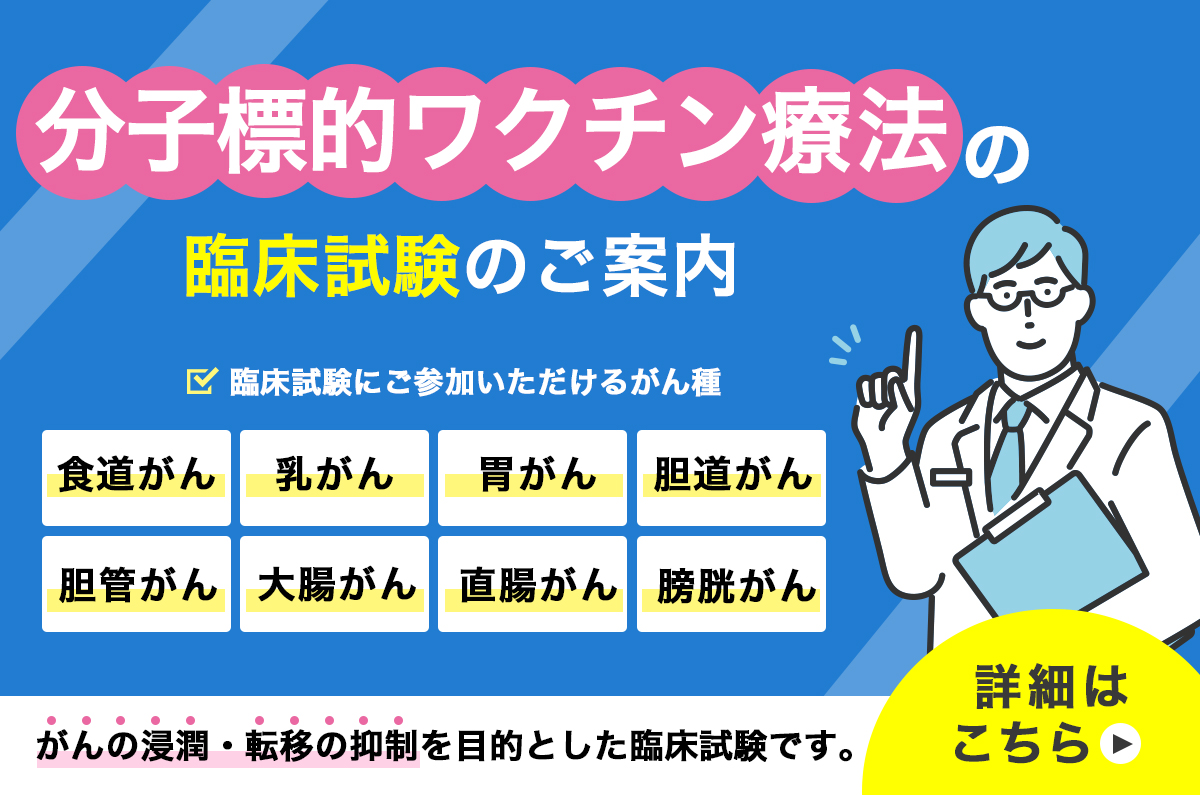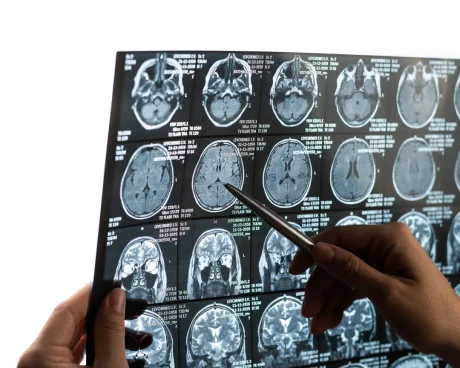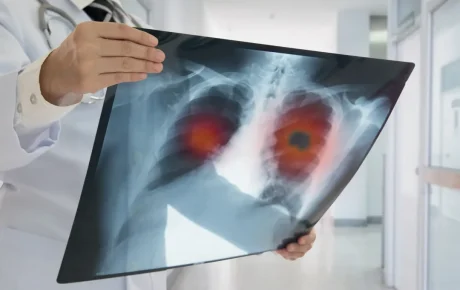子宮頸がんは、女性で比較的頻度の高いがんの一つです。2021年の女性のがん罹患数では、子宮がん全体が3万111人と第5位でした(※1)。
本記事では、妊娠中に子宮頸がんが発見されやすい理由、母体と妊娠への影響、妊娠中でも受けられる治療と検査について詳しく解説します。内容を理解し、早期発見・早期治療につなげましょう。
目次
妊娠中でも子宮頸がんは見つかる?理由と背景

妊娠中に子宮頸がんが見つかることがあります。 自覚症状がほとんどない初期の段階で、がんや前がん病変が発見されるきっかけとなります。理由と背景について詳しく見ていきましょう。
子宮頸がんの基礎知識
子宮頸がんの多くは、HPV(ヒトパピローマウイルス)の感染が原因で発症するといわれています。HPVは、性交渉経験のある女性の多くが、一生に一度は感染するとされているウイルスです。
ウイルスが排除されずに感染が長期間続くと、「異形成」といわれる前がん病変となり、数年後に子宮頸がんに進行するとされています。
20歳代後半から増加しはじめ、30代から50代で多くなるのが特徴で、初期では自覚症状がほとんどないとされています。そのため、子宮頸がん検診や妊婦健診で発見されるケースも少なくありません。
妊婦健診で発見されやすい理由
妊娠初期には妊婦健診の一環として、子宮頸がん検診が実施されます。血液検査や超音波検査と併せて行われ、その際に発見される場合もあるのです。
妊娠初期に異常が見られた場合には、精密検査が行われます。ハイリスクHPV検査(子宮頸がんを発症するリスクが高い種類のHPV感染を調べる検査)や、コルポスコープ(拡大鏡による観察)などです。
がんのステージ別に見る母体と妊娠への影響

子宮頸がんは、いくつかの組織型に分類され、主に扁平上皮がんと腺がんが挙げられます。がんが見つかった場合、妊娠を継続できるかどうかは、がんの進行状態によって異なります。
早期であれば妊娠を継続できる可能性が高く、進行している場合は治療を優先するのが一般的です。
妊娠を継続できるケース(初期がん・前がん病変)
子宮頸がんでも、極めて早期の子宮頸がん(例:IA1期)やCIN(英:Cervical Intraepithelial Neoplasia 子宮頸部上皮内腫瘍)と呼ばれる前がん病変の場合は、妊娠を継続することも可能です。
CINには段階があり、CIN1〜CIN3の3つに分けられます(※2)。CIN1=軽度異形成、CIN2=中等度異形成、CIN3=高度異形成(上皮内がんを含む)です。
子宮を残して治療するためには、一定の基準を満たさなければなりません。
緊急性がない場合は、出産を優先し、手術をせずに経過観察を行うこともあります。妊娠や出産を希望する場合は、「子宮頸部円錐切除術」が選択肢の一つとなるでしょう。
治療を優先すべきケース(進行がんの場合)
子宮頸がんがステージⅠA2期以上に進行している場合には、がんの治療が基本的に優先されます。また、がんの種類や大きさ、他の臓器への広がり具合によっては、ⅠA1期であっても子宮摘出が必要となることも少なくありません。
治療は、子宮を摘出する手術(単純子宮全摘出術)や、子宮周囲の組織も含めて切除する手術(準広汎子宮全摘出術)などが行われます。ステージがⅠB1期以降になると、手術だけでは不十分なケースもあり、放射線療法や化学療法の検討が必要になることもあります。
出産方法の選択(経膣分娩・帝王切開)
妊娠が継続できるケースでは、経膣分娩が可能なことがあります。ただし、がん部位や手術内容によっては、帝王切開の適応となる場合もあります。
子宮摘出が必要なケースでは、赤ちゃんが母親のお腹から出ても生存できる妊娠週数に達しているときは、帝王切開による出産が選ばれます。出産方法は、ご家族や主治医とよく相談して決めることが重要です。
妊娠中の子宮頸がんによる赤ちゃんへの影響
妊娠中に子宮頸がんが発見された場合、最も気になるのは赤ちゃんへの影響です。
がん治療の影響で、早産や低出生体重児として産まれる可能性はあります。現時点では、多くの研究において、妊娠中の子宮頸がんの影響による深刻な障害は報告されていません。
出生時から22カ月までの発育は、在胎週数(赤ちゃんが子宮内にいた期間)と比較しても正常だったという報告もあります。治療法と時期を適切に選べば、多くの場合で安全に出産できることが期待できるでしょう。
妊娠中でもできる子宮頸がんの治療と検査
妊娠中の子宮頸がんの治療は、進行度や妊娠週数、本人の希望などを考慮して選択されます。経過観察や円錐切除、レーザー治療、抗がん剤治療は、妊娠中でも可能です。ただし、治療のタイミングは慎重に検討する必要があります。
経過観察・円錐切除・レーザー治療
妊娠中や妊孕性(にんようせい:妊娠する力)を考慮した子宮頸がんの治療は、赤ちゃんの発育やがんの広がり(ステージ分類、進行度)によって選択されます。妊娠中でもできる子宮頸がんの検査と治療は主に以下の通りです。
| 検査・治療の種類 | 概要 |
|---|---|
| 経過観察 | ・定期的にコルポスコピーや組織検査を行い、進行していないか状態を確認する。 ・進行が見られなければ治療の開始を出産後まで待つこともある。 |
| 円錐切除術 | ・がんや高度異形成に対する治療で、子宮の温存が可能なケースもある。 ・術後は早産や低出生体重のリスクが高まるとされている。 |
| レーザー治療 | ・異型細胞病変をレーザーで焼く治療。 ・組織を採取して詳しく調べることができないため注意が必要。 ・基本的に前がん病変(CIN/上皮内がん)を対象としており、浸潤がんが疑われる場合は適応外。 |
抗がん剤治療のタイミングと胎児への影響
妊娠中でも時期を選べば投与できる抗がん剤もあります。投与するタイミングによっては、お腹の赤ちゃんの発育に影響を及ぼすおそれがあるため、注意が必要です。
妊娠中に抗がん剤を使用できるのは、妊娠中期以降が一般的です。
妊娠初期は赤ちゃんの成長発達に重要な時期であり、このタイミングで抗がん剤を投与すると先天異常のリスクが高まります。また、分娩前の投与を避ける必要があるため、少なくとも予定日の3週間前までには中止していることが望ましいとされています(※3)。薬剤の選択やスケジュールは、母親と赤ちゃんの安全を最優先します。
帝王切開後の子宮摘出
赤ちゃんが母体の外で生活できると考えられる週数は、妊娠22週以降で、医療機関のNICU体制によって判断が異なる場合があります(※4)。
子宮頸がんが見つかった場合、基本的に出産を優先して計画されます。帝王切開で出産後に、子宮を摘出することも検討します。これは、赤ちゃんと母親の命を守り、がん治療を進めるための措置です。妊娠週数や進行度、患者やそのご家族の意向を踏まえたうえで進められます。
出産後にもう一度妊娠できるのか

子宮頸がんの治療後に、再び妊娠・出産できるかどうかは、選択した治療法によって異なります。将来妊娠を希望する場合は、子宮を残す治療法や妊孕性を温存する方法を選ぶことで、妊娠の可能性が広がるでしょう。
子宮を残す治療法
子宮頸がんの診断を受けても、将来妊娠や出産を希望する方にとって、子宮を温存できるかどうかは重要な問題です。円錐切除術や温存手術によって子宮を残すことができれば、将来的に妊娠する可能性が残ります。
しかし、子宮を摘出しない場合、がんの再発リスクが高まる可能性があります。治療法を決定する際には、主治医と十分に話し合うことが重要です。
妊孕性温存の選択肢(卵子・胚凍結)
子宮頸がんの治療後に妊娠や出産を望む場合は、妊孕性を温存することも選択肢の一つです。パートナーがいる場合は、治療前に胚(受精卵)の凍結保存を行います。パートナーがいない場合には、未受精卵の凍結保存が検討されるでしょう。がんの治療後、体外受精や顕微授精などの生殖補助医療を受けられます。
妊娠中に子宮頸がん検査に引っかかったときに最初にすべきこと
妊娠中に子宮頸がん検査で「異常あり」と診断されると、大きな不安を感じるのは当然です。一人で抱え込まずに、できるだけ早く医療機関を受診することが大切です。
まずは、かかりつけの婦人科医やがん治療経験のある専門医に相談しましょう。医療機関では精密検査を行い、病変の状態を確認します。診察結果をもとに、経過観察にするか、すぐに治療を始めるかが判断されるでしょう。がんのステージや病変の大きさ、妊娠週数、妊娠継続の希望などを総合的に考慮して決定されます。パートナーやご家族、主治医と十分に相談し、納得できる選択肢を見つけることが何よりも重要です。
妊娠中に子宮頸がんになったらまずは主治医と相談を

妊娠中に子宮頸がんになった場合、治療法や出産までの流れを主治医と十分に相談することが大切です。進行状況によっては、出産が可能なケースもあります。安心して出産に臨めるよう準備を進めていきましょう。
主治医がいない場合や相談しづらい場合は、がん専門の相談センターを利用するのも方法の一つです。
(※1)国立研究開発法人国立がん研究センター|子宮
(※2)国立がん研究センター|子宮頸がん 治療
(※3)日本婦人科腫瘍学会|子宮頸癌治療ガイド2022年版
(※4)日本産婦人科医会|人工妊娠中絶の定義