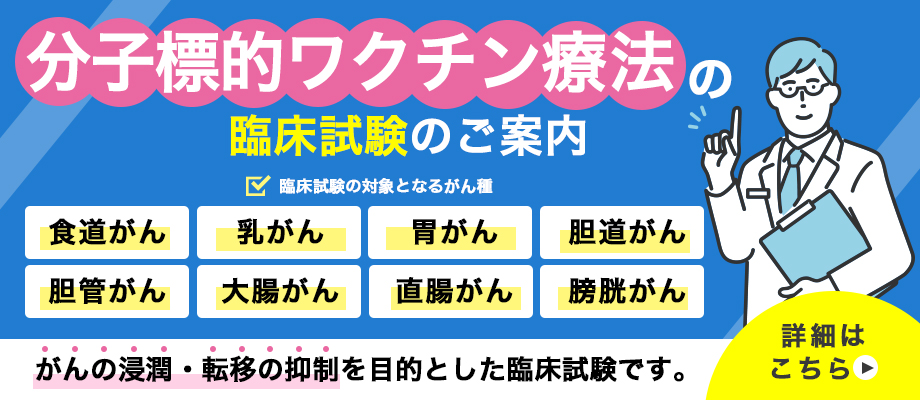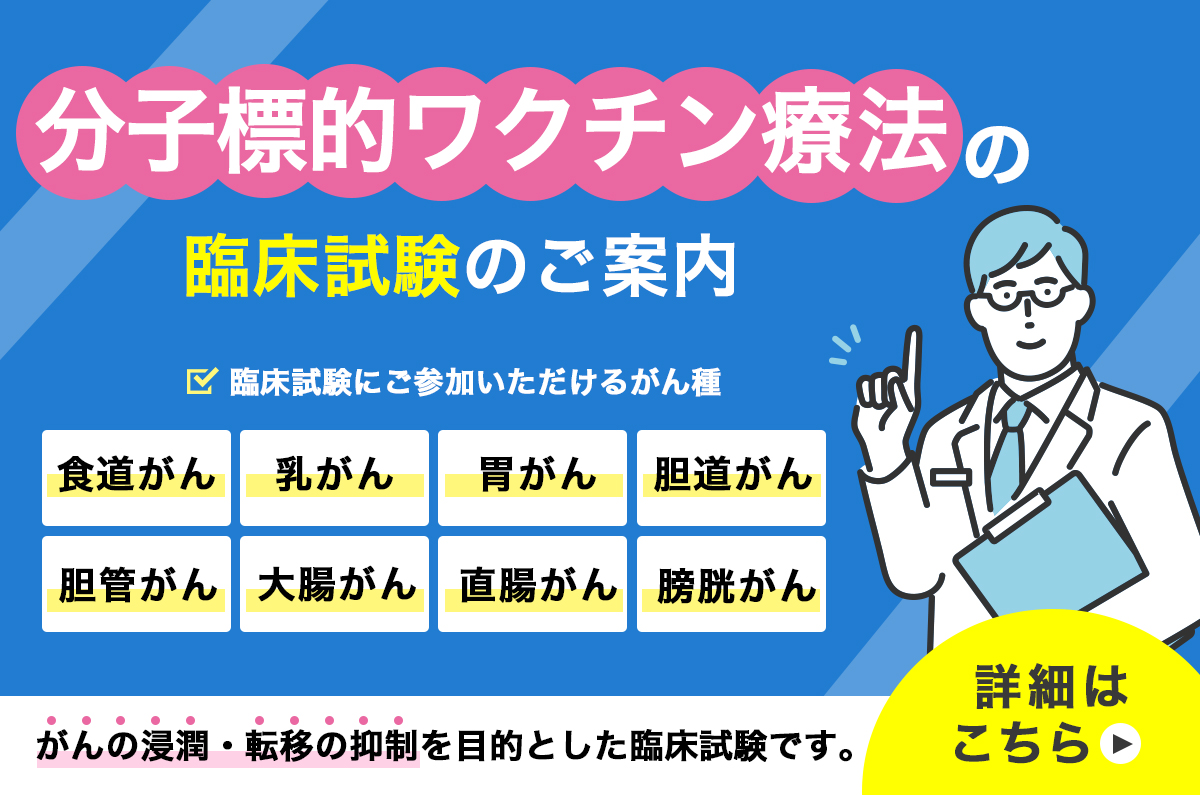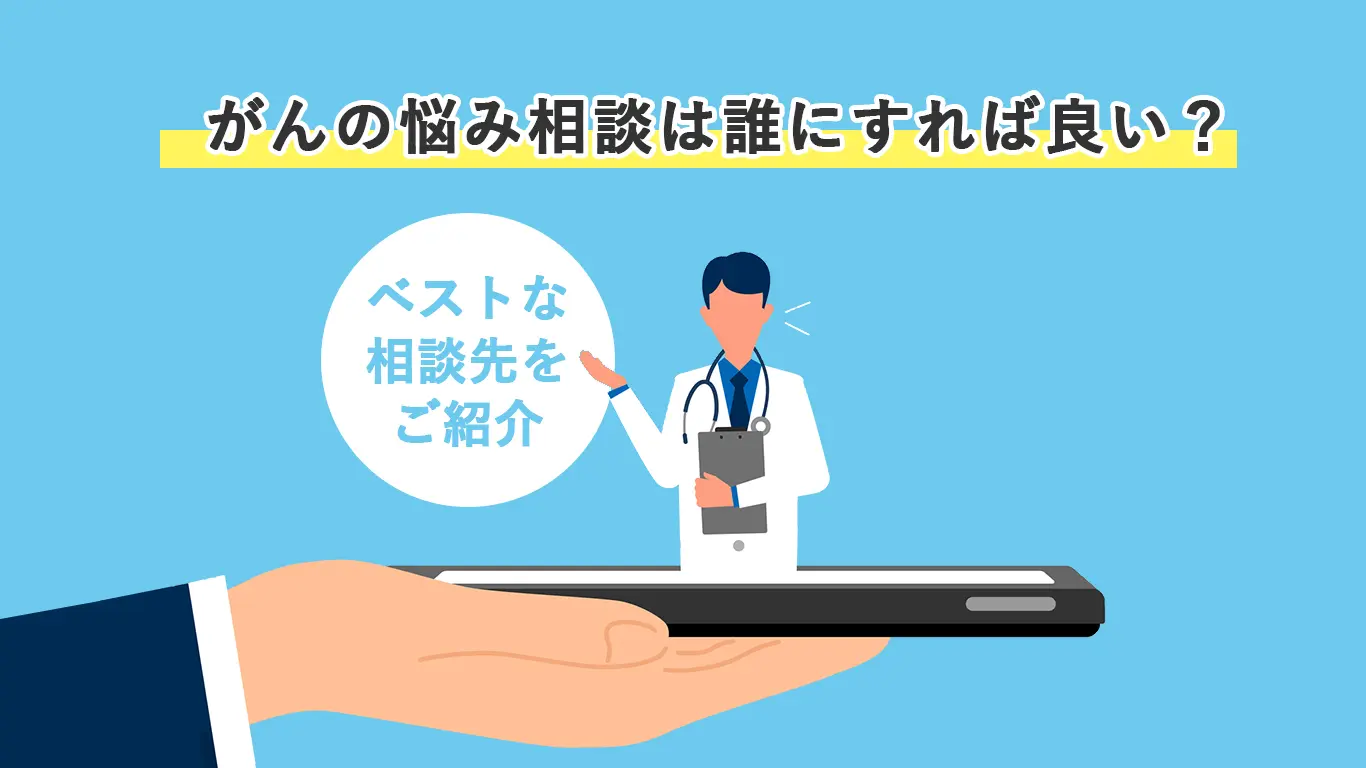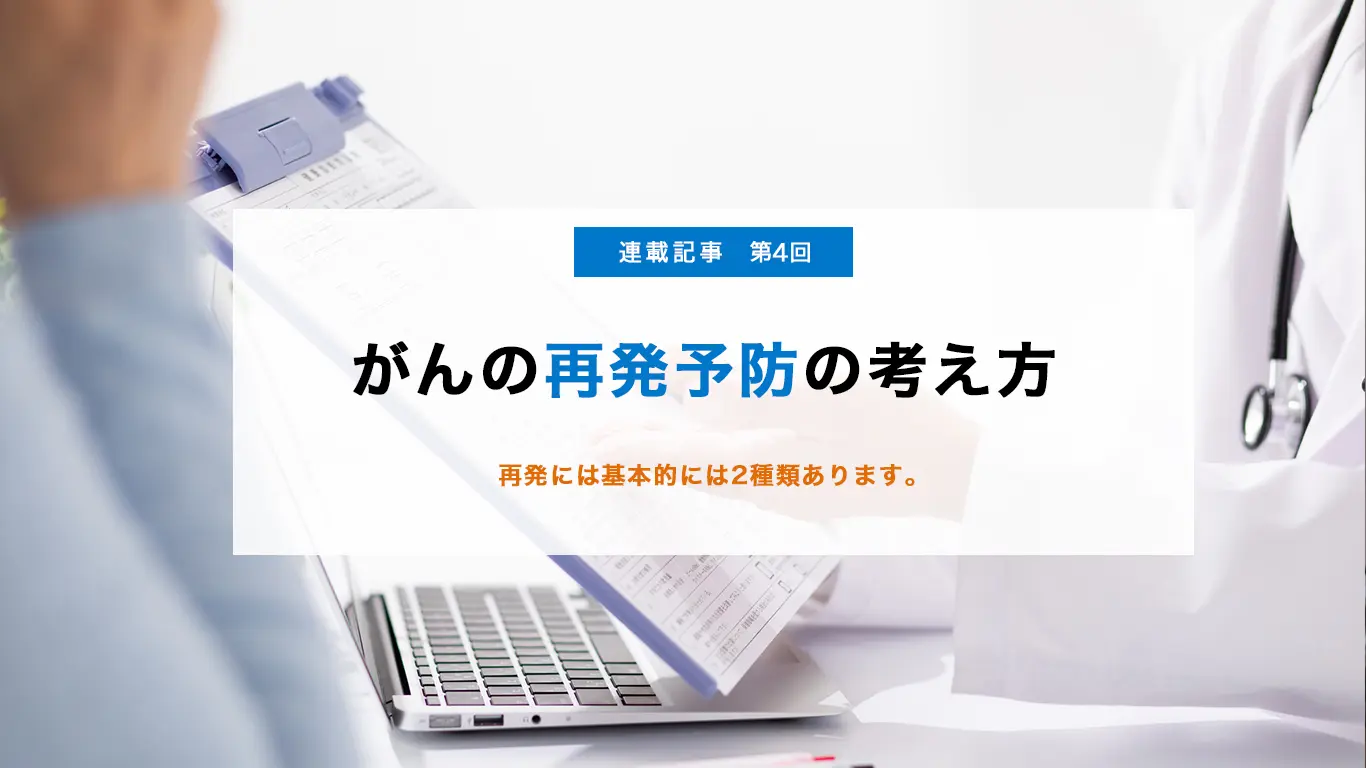「子宮頸がんワクチンを打って後悔した」という声を目にし、不安になった方もいることでしょう。
子宮頸がんワクチンには、子宮頸がんの原因となるHPV(ヒトパピローマウイルス)を防ぐ効果があるといわれており、世界保健機関(World Health Organization:WHO)でも接種を推奨しています。
日本では2010年に子宮頸がんワクチンの公費助成が開始されましたが、副反応が疑われるケースが相次いだことによって、2013年から2021年の間は一時的に勧奨が控えられていました。その後、安全性が確認されたことによって、2022年4月から公費接種が再開しました(※1)。
本記事では、子宮頸がんワクチンの効果や副反応、「後悔した」という声の実態について解説します。
目次
子宮頸がんワクチン接種への不安の声

ここでは、SNSやネット上で見られる「子宮頸がんワクチンを打って後悔した」という声について、医学的な根拠や統計データをもとに解説します。
「子宮頸がんワクチンで後悔した」という声の実際
SNSやネット上には「子宮頸がんワクチンを打って後悔した」という口コミが存在しており、主な症状として以下が報告されています。
- 関節痛、けいれん、視力低下
- 自律神経失調症状(耳鳴り、めまい、動悸など)
- 不随意運動(意思と関係なく身体が動く)
実際に日常生活に支障をきたす、回復までに長い時間を要するといったケースが存在しているのも事実です。しかし、これらの症状はワクチンを接種していなくても見られることがあります。 また、副反応のみを強調した報道や根拠のない情報も不安をあおる要因になっていると考えられるでしょう。
副反応に関する統計データ
子宮頸がんワクチンには、2価ワクチン(サーバリックス)・4価ワクチン(ガーダシル)・9価ワクチン(シルガード9)の3種類があります(※2) 。
2価 ・4価 ワクチンはHPV16型と18型の感染を防ぐことが可能とされており、これは子宮頸がんの原因とされるHPVの約50%から70%をカバーしているといわれています。
これらに加えてさらに5つの型(31型、33型、45型、52型、58型)に対応している9価ワクチンは、約80%から90%を予防できるとされています(※3) 。
副反応の出現率は1万人あたり2価・4価ワクチンで約9人(うち重篤者約5人)、9価 ワクチンで約5人(うち重篤者約3人)と、いずれも発生率は低いといえるでしょう(※3) 。
子宮頸がんワクチンの有害事象・副反応

子宮頸がんワクチン接種後に起こる可能性のある症状について解説しましょう。
一般的な症状とその発生率
子宮頸がんワクチン接種後に起きた症状として報告された例として、以下が挙げられます。
- 接種部位の疼痛(とうつう)・発赤(ほっせき)・腫れ・かゆみ
- 疲労・倦怠感
- 発熱
- 頭痛
- 下痢・嘔吐
- 失神
- めまい など
接種部位に見られる局所的な症状は、約8割以上の方に起こるとされています(※4)。 また、注射時の不安や痛みなどによって迷走神経反射を起こし失神することがありますが、これらは一時的な症状です。
一方で、全身症状とワクチン接種との因果関係は明らかになっておらず、 その多くは「機能性身体症状」であると考えられています。
機能性身体症状とは、 知覚・運動・認知機能などに影響を及ぼす症状があっても検査で異常が見つからない状態のことであり、不安や疼痛が原因であると考えられています。
重篤な症状とその発生率
子宮頸がんワクチン接種後に重篤な症状が出現したとして、以下の疾患が報告されています。
- アナフィラキシーショック:アレルギー反応
- ギランバレー症候群:筋力低下、しびれなど
- 急性散在性脳脊髄炎(ADEM):神経症状
子宮頸がんワクチン接種後の発生頻度については、アナフィラキシーショックは約96万回接種のうち1回、ギランバレー症候群・急性散在性脳脊髄炎(ADEM)は約430万回接種のうち1回程度 だとされています。接種頻度からして、非常にまれといえるでしょう(※5) 。
2013年に中止された接種推奨、2022年に再開した理由

ワクチン接種の推奨が一時中断されてから再開されるまでに、以下の点が確認されました。
- 副反応対策の強化:安全性評価の体制整備や専門医療機関の設置が進んだ
- 「接種控え世代」のリスク増大:ワクチン未接種世代のHPV感染率や子宮頸がんリスクの上昇が明らかになった
- WHOと日本の安全性評価:ワクチンの副反応の一部はストレス反応によるものであり、ワクチンに含まれている成分自体の影響ではないと判断された
接種勧奨の再開後も、販売前の承認調査、ロットごとの点検、予防接種後の定期的なモニタリングによって、安全管理がさらに徹底されるようになっています。
子宮頸がんワクチン「キャッチアップ接種」とは
2025年3月時点、2013年から2022年にかけて接種する機会を逃した、いわゆる「接種控え世代」(1997年4月2日から2008年4月1日生まれ)の女性を対象とした、「キャッチアップ接種」を行っています(※6) 。
2025年3月末までに1回目を接種し、2026年3月末までに残りの接種を完了する必要があるため、接種対象となる方は自宅に届いた自治体からのお知らせを確認し、接種を検討しましょう(※6) 。
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~|厚生労働省
ワクチン接種後に副反応が疑われたときの対応について

子宮頸がんワクチン接種後に有害事象が生じた際の対応方法について解説します。
「副反応かも?」と思ったらまずは医師へ相談を
ワクチン接種後に副反応が疑われる場合、接種を受けた医療機関や、かかりつけ医に相談しましょう。
症状は数日以内に軽快するケースもありますが 、症状が長引く、程度が強いという場合には早めに医師へ相談することが必要です。
ワクチン健康被害救済制度の利用は市町村へ申請を
子宮頸がんワクチンを含む各種予防接種による健康被害の発生に備え、国では「健康被害救済制度」を設けています。
これは、ワクチン接種後の体調不良とワクチン接種との因果関係が認められた場合に、自治体から医療費や障害年金などの給付を受けられる制度です。
ワクチン接種後に健康被害が疑われる場合、お住まいの市町村に審査を申請します。
子宮頸がんワクチンに関するよくある質問
子宮頸がんワクチンに関するよくある質問とその回答について、ご紹介します。
Q.性行為の前にHPV検査や細胞診を受けて陰性であれば、ワクチンは打たなくてもいいですか?
A.すでに性交渉の経験があっても、ワクチンを接種することで未感染のウイルスを予防する効果があるといわれています。また、HPV検査や細胞診が陰性であっても、将来的な感染リスクを防ぐ目的でワクチン接種が推奨されています。
Q.子宮頸がんワクチン接種を親に反対されます。どうしたらいいのでしょうか?絶対に受けなければならないのでしょうか?
A.子宮頸がんワクチンの効果は証明されていますが、接種は必須ではありません。あくまでも個人ならびに保護者の方の意思に基づいて行われるものです。 まずは、ワクチンに関する正しい情報をもとに、保護者の方とよく話し合うことが大切です。厚生労働省が発行しているリーフレットを活用してみてください。
【概要版】
概要版 小学校6年生~高校1年相当の女の子と保護者の方への大切なお知らせ|厚生労働省
【詳細版】
詳細版 小学校6年生~高校1年相当の女の子と保護者の方への大切なお知らせ|厚生労働省
Q.子宮頸がんワクチンは風邪のときに接種しても大丈夫ですか?
A.風邪をひいているときの子宮頸がんワクチン接種の可否については、必ず医師へ相談しましょう。発熱がある場合は日程を改めることがあります。
Q.16歳を過ぎてから接種しても効果はありますか?
A.国内外の研究では、初回性交渉前に子宮頸がんワクチンを受けることが推奨され ています。とはいえ、16歳を過ぎてからの接種でも、効果が見られないわけではありません。スウェーデンの調査報告では、17歳未満で接種を受けた女性では、子宮頸がんが88%減少し、17歳から30歳で接種した女性のうち53%の減少を認めたと報告されています。
子宮頸がんワクチンの正しい知識を持ち、後悔のない決断を
子宮頸がんワクチンは、HPV感染を予防し、将来的な子宮頸がんのリスクの低下効果が確認されている一方で、副反応のリスクや接種に対する不安を持つ方も少なくありません。
SNSやネット上の情報の全てが正確ではないため、厚生労働省など信頼できる医療情報をもとに、正しい知識を身につけ、後悔のない選択をしましょう。
(※1)厚生労働省|医療従事者の方へ ~HPVワクチンに関する情報をまとめています~
(※2)厚生労働省|ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~
(※3)厚生労働省|詳細版 小学校6年生~高校1年相当の女の子と保護者の方への大切なお知らせ
(※4)公益社団法人 日本産科婦人科学会|子宮頸がんとHPVワクチンに関する正しい理解のために
(※5)厚生労働省|HPVワクチンに関するQ&A
(※6)厚生労働省|ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~