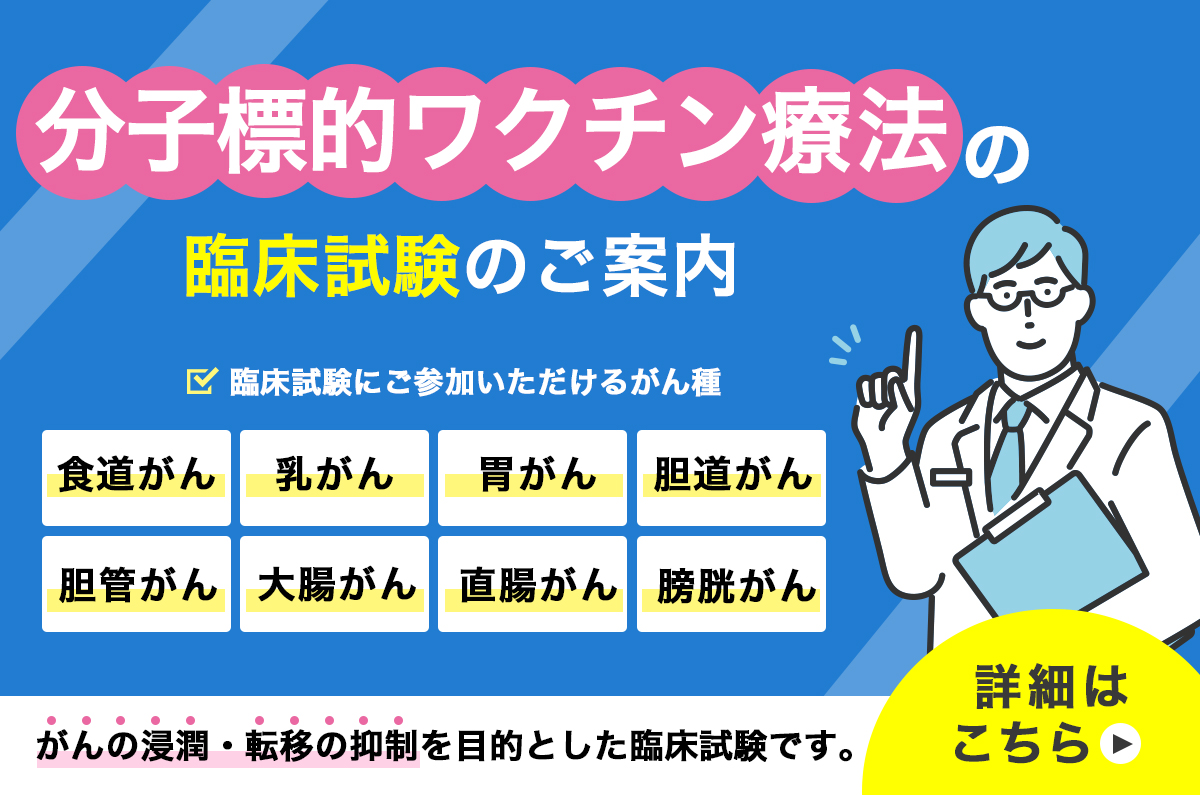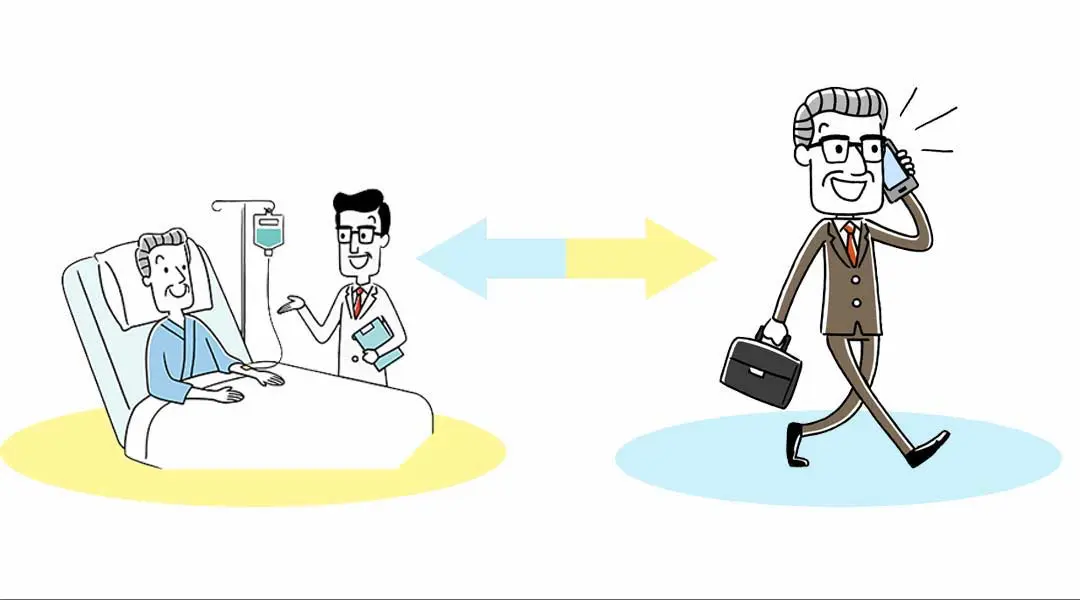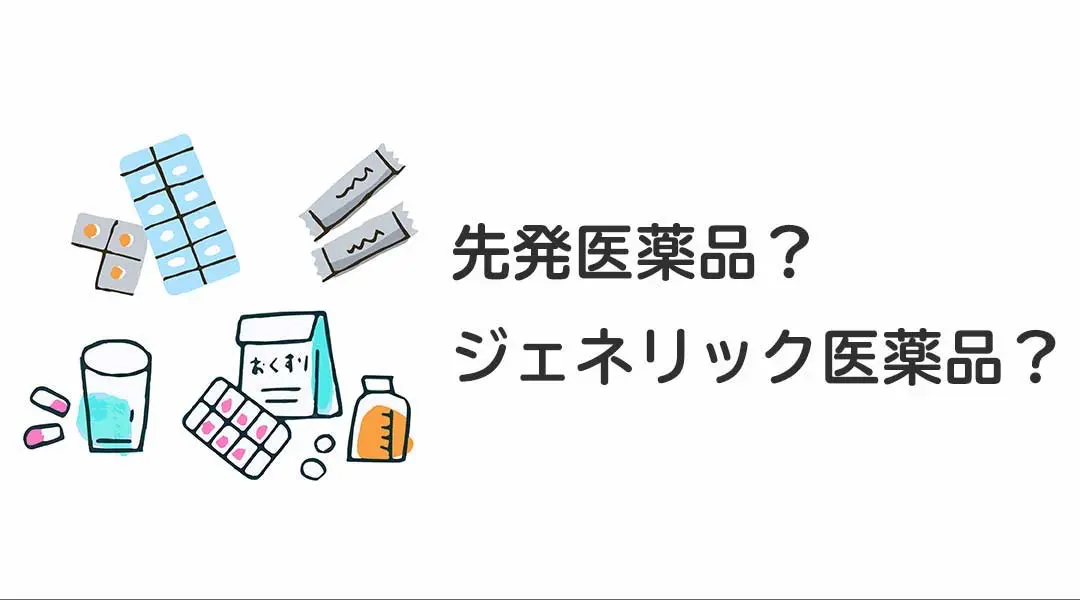この記事は前回の記事「がんの正体と抗がん剤治療の仕組み」と合わせてお読みいただければ、より抗がん剤についての理解が深まるようになっていますので、そちらもご確認下さい。
がんの治療は手術・放射線・抗がん剤からなる三大標準治療というものを軸にしています。
今回はその一つである抗がん剤についてご説明します。
抗がん剤は前回の記事でご説明した増殖、転移といったがんが持つ性質を抑えたり予防するために使われる薬です。他の二つと決定的に違うのは、手術、放射線が局所治療であるのに対し、抗がん剤は全身治療という点です。
局所治療は局所(=一か所に限られた)がんのみに有効ですが、がんはいつまでも一か所にとどまっていませんので、がんと診断されたタイミングですでに転移が見つかった場合、あるいは治療しているにも関わらず進行してしまったケースでは全身に効果が見込める抗がん剤が大切な治療となるのです。
そのように重要なポジションである抗がん剤には様々な種類があり、さらに近年副作用を軽くしたり、効果を高めるためにますますその種類は増えています。
目次
抗がん剤とは
現在世界各国で作られている抗がん剤の種類は数百にも及ぶと言われています。日本でも厚生労働省の承認済み・未承認を含めて150種類以上の抗がん剤が使用されています。
抗がん剤は大きく3つに分けることができます。
- 細胞阻害性抗がん剤
- 分子標的薬
- ホルモン剤
以下、それぞれの特徴や役割を分かりやすく解説させて頂きます。
細胞阻害性抗がん剤
従来からある抗がん剤です。皆様が想像する「抗がん剤を投与すると副作用に苦しむ…」というイメージはこの抗がん剤からくることが多いと思います。この抗がん剤をさらに細かく分けると、代謝拮抗剤、アルカル化剤、抗がん剤抗生物質、植物アルカロイド、プラチナ製剤の5種類になります。
がんは生きるために細胞分裂し大きく成長していきますが、その様々なタイミングで細胞が分裂するのを邪魔して阻害することでがん細胞の増殖を防ぎ、がん細胞を殺します。その阻害方法で上記のように分けることができます。
通常、抗がん剤は多剤併用といって数種類の薬を併せて使用しますが、このとき、代謝拮抗剤から1剤、アルカル化剤から1剤というように阻害方法が違う薬剤を組み合わせて使用します。これはいろいろな角度からがん細胞を攻撃し、相乗効果を狙うためです。
抗がん剤は基本的に飲む、あるいは注射することで体内に投与します。このほかにも皮膚に塗ったり貼付剤として貼ることもありますが圧倒的に服用するか注射で投与することが多いです。そして体内に入った薬が血流に乗ってがん細胞まで運ばれダメージを与えますので、体の複数の部分に広がった状態での治療も可能です。
抗がん剤を体内に入れると、がんを殺すと同時に正常な細胞にもダメージが及びます。これが抗がん剤で副作用が出る理由です。がん細胞を全滅させるだけの抗がん剤を使用すると正常な細胞も多大な影響を受けますので患者さん自身の体がもちません。このため、抗がん剤治療はがんを完全に攻撃するのではなく、がんの成長を食い止めることが目標となります。がんの進行を食い止め、それ以上大きくなったり新たな転移を防ぐことで患者さんのQOLを保つことができます。
抗がん剤が効いているとはどういうこと
風邪薬でさえ「効き目が長く続く」「この薬は効かなかった」などとよく言います。抗がん剤も効果が出る、出ない、効果が薄れるということはもちろんあります。抗がん剤の治療効果を腫瘍マーカーのように血液検査の結果で判断することはできません(血液がんは例外で、がん細胞の数を直接計測して判定します)。抗がん剤の効果判定の見方は少し特殊で、がんの面積の変化で測定します。
・消失
・面積半分
・大きさそのまま → 効いている(→抗がん剤を継続・中断)
・面積5割増し → 効いていない(→抗がん剤の種類変更)
このように使用後と使用前のがんの面積を比較することによって効果が出ているかどうか確認します。がんは何も治療をしなければ大きくなる一方ですから、抗がん剤を使用して大きさが変わらなくても、その抗がん剤には効果があったとみなします。
基本的に効果が出ていて副作用も我慢できるほど(血液検査の値も異常がなければ)であれば、引き続き同じ抗がん剤を使用します。効いていなければ種類を変えて改めて様子を見ます。効果が出るかどうかは使用してみないと正確にわかりませんが、これまでの膨大なデータから効果が出やすい種類はわかっていますので、可能性の高いものから使用するのが一般的です。
分子標的薬
分子標的薬は2000年ころから使用が開始された比較的新しい抗がん剤です。細胞阻害性抗がん剤のような従来の抗がん剤は生きた細胞を傷つけたり殺したりする、いわゆる細胞毒性という性質によって治療の効果を得てきました。それに対し分子標的薬は、がんの成長や増殖にとってのキーポイントとなる「分子」の働きを邪魔することでがんの成長を抑える薬です。
近年、がんに関する研究が進みそのメカニズムが解明されてきたことにより、がんは遺伝子の病気であることがわかり、がん細胞が増殖するのは傷ついた遺伝子に存在する異常な物質が悪さをしているためであることがわかりました。分子標的薬はその名前の通り異常な物質(=分子)を標的にする抗がん剤です。この物質というのは、がん細胞が増殖するのにかかわっている物質で、がん細胞の表面だけに(あるいはがん細胞に目立って)見られる遺伝子のことです。分子標的薬はこの遺伝子を狙って薬が届くように設計されています。
患者さんにとってのメリットは何といっても副作用が抑えられる可能性が高いということです。特定の遺伝子をピンポイントで狙い撃ちすることでなるべく正常な細胞を守ることができますので、どんな細胞でも攻撃してしまう従来の抗がん剤に比べ副作用が軽度だと言われています。(重篤な副作用が出る場合もあります)
また、同じがんでも、その遺伝子がある細胞と無い細胞があり、その有無は検査であらかじめわかりますので、効果が見込めるかどうか最初から確認できます。この検査のことを遺伝子検査といいますが、例えば肺がんの患者さんは肺がんの診断を受けたあと、遺伝子検査を行い、陽性であればイレッサという分子標的薬で効果が期待できるため使用するという流れとなります。
しかし、陽性であっても全てのがん細胞に特定の遺伝子があるわけではなく、中には特定の遺伝子を持たない細胞があります。分子標的薬が攻撃できるのは特定の遺伝子がある細胞だけですので、それ以外の細胞には効果が見込めません。それゆえ、従来の抗がん剤よりもある程度までは効果が出る可能性は高いものの、分子標的薬でがんを完全に治すというのは難しいでしょう。
ホルモン剤
男女の生殖器のがんに使用される抗がん剤です。主に性ホルモンで成長する男性の前立腺がん、女性の乳がん、子宮体がん、卵巣がんで使用されます。
ホルモンは人間の体の状態を調節する物質です。例えば暑さで体が水分を失ったときには抗利尿ホルモンというホルモンが分泌され、尿の量が減ります。また、女性は女性ホルモンの働きによって子宮が周期的に妊娠の準備をし、月経が起こります。生殖器のがんも同じようにホルモンの影響を受けたり、がん細胞の餌となります。そのため基本的にホルモン剤は、がん細胞の増殖を促す性ホルモンの働きを妨げる作用を利用した治療です。
ホルモン剤はがんを殺傷するのではなく、がんの増殖をストップさせて休眠状態にさせる薬ですので、ホルモン剤でがんが完全に治療することはありませんが病状の改善やがんの進行を停止させたり遅らせることができます。がんが治癒しなくても、ホルモン剤のみで10年以上の延命を期待することもできます。
ホルモン剤にもいくつか種類があります。
性ホルモン剤
逆の性のホルモンは、性ホルモンの働きを妨げます。例えば男性ホルモンによって増殖するがんに対しては女性ホルモンを投与し、女性ホルモンによって増殖するがんに対しては男性ホルモンを投与します。また同じ女性ホルモンでもエストロゲンとプロゲステロンは互いに相殺する作用を持っています。そのためエストロゲンで成長するがんにはプロゲステロンがその成長を抑える効果を示すことがあります。
抗ホルモン剤
がん細胞の核(細胞の中央にある卵でいう黄身のような部分)にはホルモンを受け取る物質が存在することがあり、これがホルモンと結びつくと増殖の信号が発信され、がんが増殖します。そこで代わりにホルモンに似た物質をがんに送り込むと、この物質がホルモンと同じように結びついてがん細胞は増殖する信号を受け取れなくなります。
ホルモン生成阻害剤
性ホルモンの生産を止める薬です。酵素によって活性化するホルモンががんを増殖させることがあるため、この酵素の働きを妨げることによってホルモンの生産を抑える薬です。
ホルモン分泌阻害剤
脳の下垂体はLH-RHというホルモンを分泌し、それが精巣や卵巣を刺激するホルモンの分泌を促します。そこでLH-RHの働きを抑えるのがホルモン分泌阻害剤です。この抗がん剤によりLH-RHを受け取る受容体の数が徐々に減っていきその結果、性ホルモンの分泌も減少します。
生殖器のがんでもホルモンによって成長しないタイプのものもありますので、その場合にはホルモン剤による効果が見込めません。例えば、乳がんは「サブタイプ」といって効果が見込める治療別のカテゴリーに分けることができます。これは、がんの一部を採取して顕微鏡で詳しく検査することでわかるのですが、ホルモン剤が効くタイプにあてはまった人だけがホルモン剤を使用するということになります。
ホルモン剤は比較的副作用が軽い抗がん剤です。しかし、ホルモンの働きを抑えるため更年期障害の症状が現れることがあります。例えばほてりやのぼせ、めまい、頭痛、男性は性欲の減退などです。その他、稀に血栓症や心臓の障害を起こすこともあります。
おわりに
医療が進歩し、がんのメカニズムが解明されつつあることに併せて、抗がん剤もより精密なものに改善されてきましたが、同時にその限界も明らかになってきました。抗がん剤は、まだ多くの場合がんを完治させるには至りません。副作用の問題も残されています。
しかしながら分子標的薬の登場を見ても、ここ数年の間に着実にがんを治しやすい治療に近づいてきていると感じています。また手術や放射線の技術、機械の革新もありますので、それらとの併用治療により、がんは恐ろしい病気ではなくなるのも時間の問題ではないかと思います。
現在治療を受けていらっしゃる方は、医師の十分な説明のもとに治療をされていらっしゃるはずですが、自身で知識を得ようとすることも大事だと思います。使用している抗がん剤に疑問を感じた時、あるいは新しい抗がん剤を提案された時、この記事を治療の参考にしてみてください。