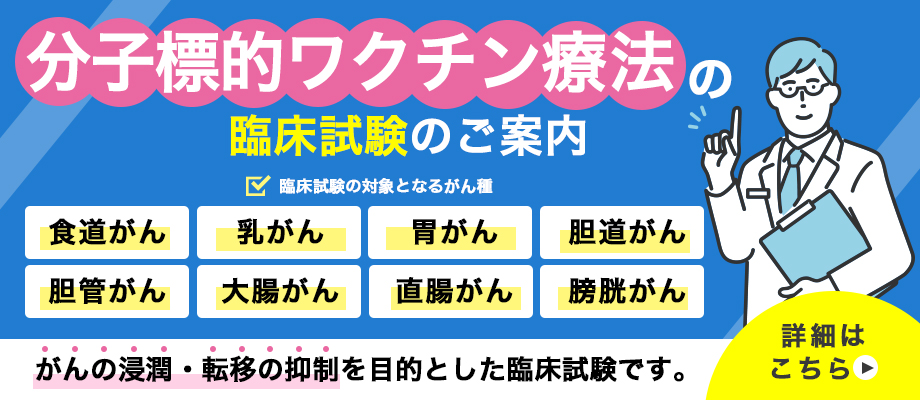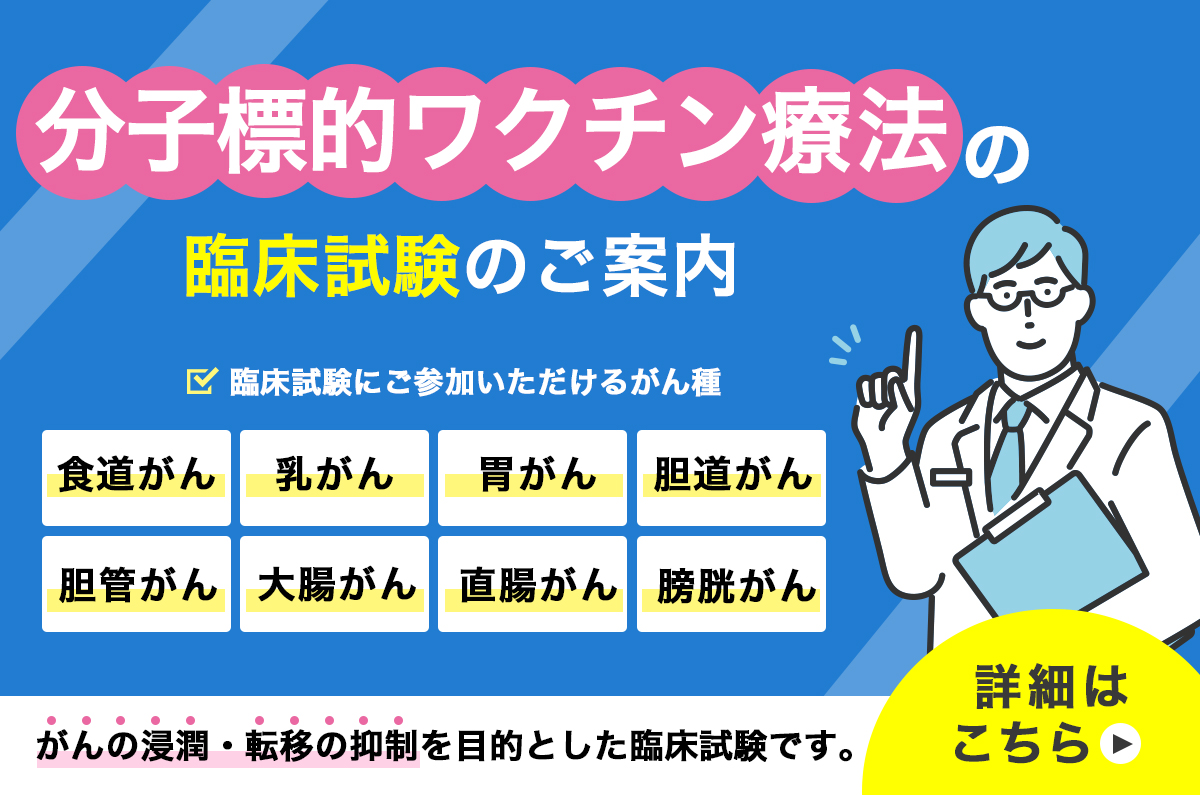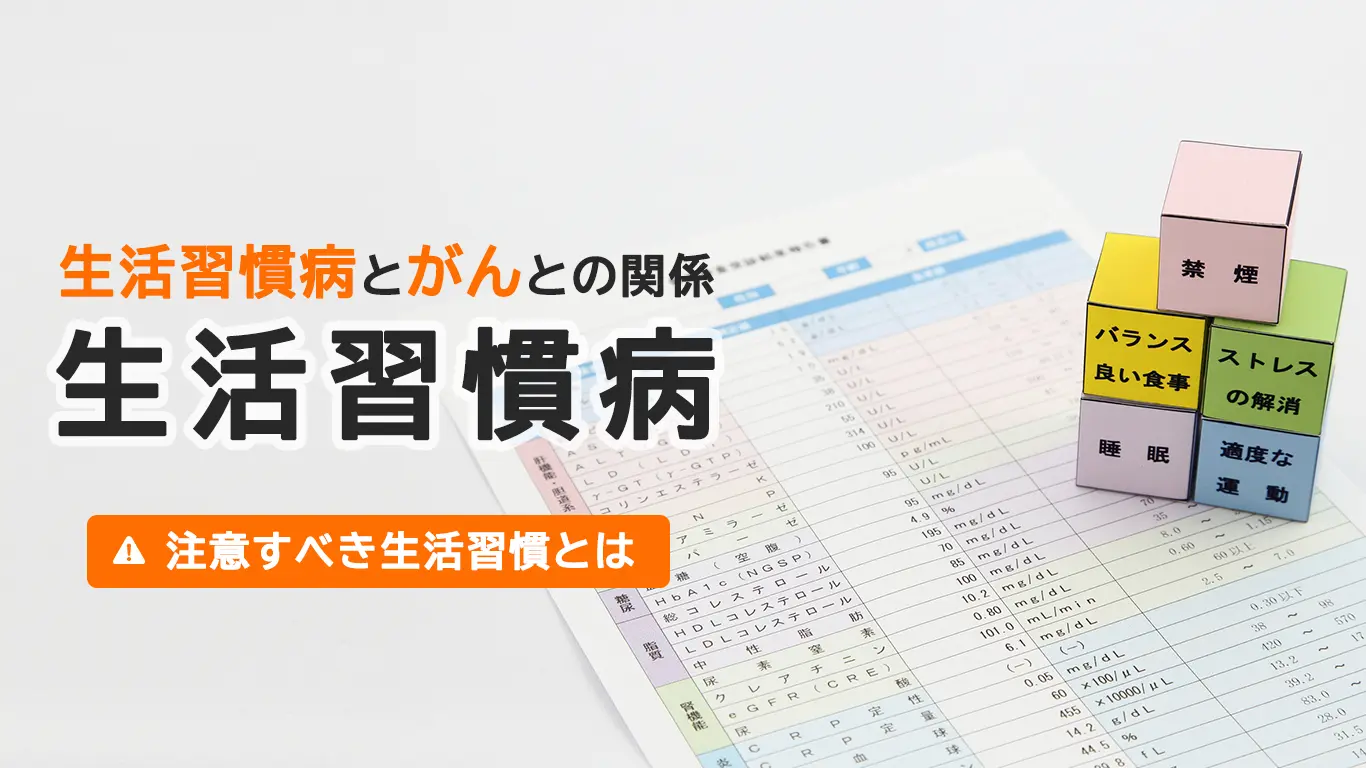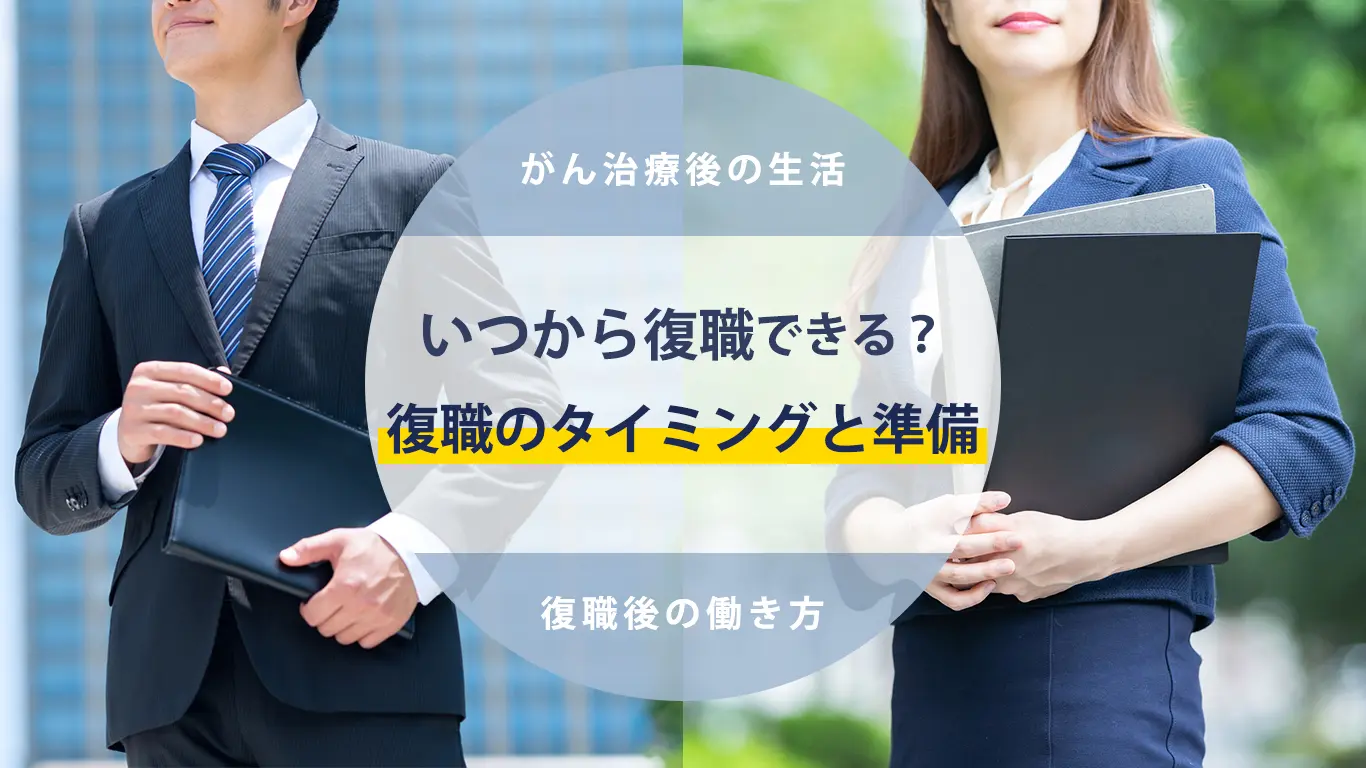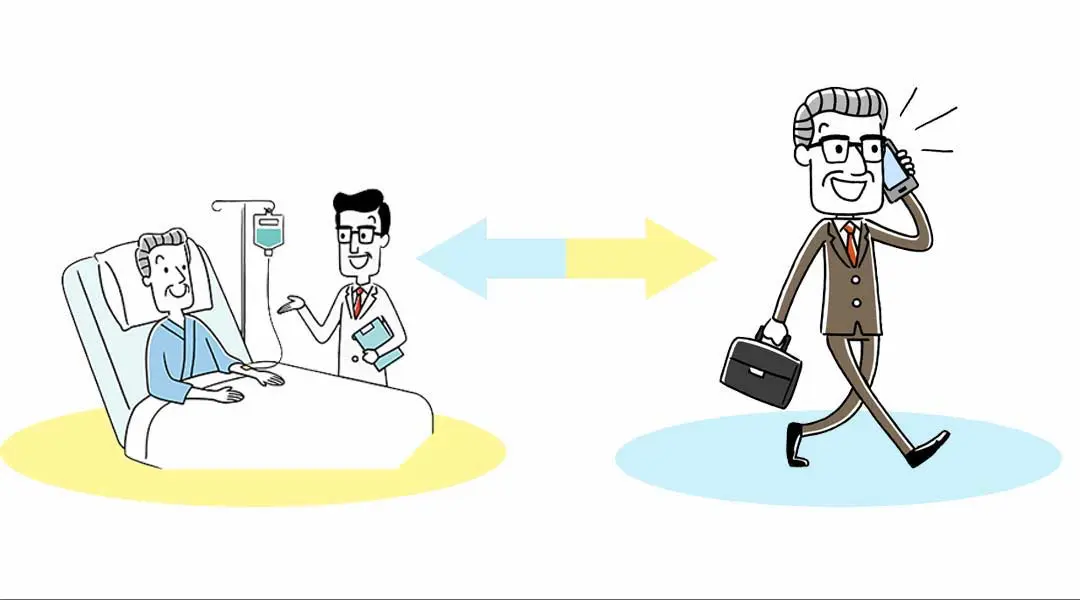日焼けは肌に悪いということは多くの方がご存じのことではないでしょうか。そのイメージ通り、日焼けはさまざまな形で肌に害を与えるとされています。一時的な痛みや赤みだけであれば大きな問題はありませんが、日焼けの跡が消えても少なからず何らかの影響は残ります。
本記事では日焼けと皮膚がんの関係について詳しくお伝えします。
目次
日焼けと皮膚がんの関係

日焼けと皮膚がんの関係について詳しく見ていきましょう。日焼けをしすぎると、皮膚がんになりやすくなるのでしょうか。
日焼けとは
日焼けとは、肌の炎症反応のことを指します。太陽光に含まれる紫外線を浴びることで、肌が炎症を起こして赤くなる状態のことを「日焼け」と呼びます。つまり、日焼けとは紫外線による軽い火傷のようなものといえるでしょう。
日本では、一般的に「日焼け」と一括りにされていますが、実際には2種類に分けられます。
まず、ひとつが紫外線を浴びてから数時間後から起こる「サンバーン(Sunburn)」で、皮膚が赤くなり、8時間から24時間で痛みが伴い、2日から3日で消えるとされています(※1)。
もうひとつの日焼けは、紫外線を浴びてから数日後に起こる「サンタン(Suntan)」です。痛みはほとんど生じないとされていますが、皮膚が浅黒く変色した状態が数週間から数カ月続くといわれています(※1)。
紫外線を浴びるとがんが発生しやすくなるメカニズム
結論から言えば、紫外線を浴びると、つまり日焼けをすると皮膚がんのリスクは高まります。
紫外線を浴びると、皮膚の細胞のDNAが傷つけられます。ただし、細胞にはDNAを修復する機能が備わっているため、紫外線を浴びても人体に何らかの問題が起こるわけではありません。
主となる問題は、紫外線を繰り返し浴びているケースです。
このような場合、皮膚細胞が何度も傷つけられることで、DNAの修復ミスが一定確率で発生し、やがて「細胞の突然変異」につながることが考えられます。
例えば、がんの発生に関連する遺伝子に突然変異が起こった場合、がん細胞が徐々に増殖し、皮膚がんになるというリスクが高まる可能性があります。
日焼けによって生じる皮膚疾患の種類と特徴

日焼けをすると皮膚にどのような影響をもたらすのでしょうか。ここでは、日焼けによって起こり得る皮膚疾患の種類とその特徴についてお伝えします。
日光角化症
日光角化症とは、その名の通り、日光(紫外線)の影響によって皮膚に生じる「前がん病変(※将来的にがんに進行する可能性がある病変)」のひとつです。皮膚の表面がかさつき角質化し、かさぶたが生じることから「角化症」と呼ばれています。
日焼けをしても肌が黒くなりづらい方が、発症しやすいのが特徴です。発症部位は紫外線の影響を直に受ける顔が最も多くなりますが、手の甲や頭部の発症も少なくありません。
有棘細胞がん
皮膚は、外側から順に表皮、真皮、皮下組織の3層で構成されていますが、有棘(ゆうきょく)細胞がんは表皮にある有棘細胞が悪性化してできるがんを指します(※2)。主な症状は、皮膚表面のかさつき、盛り上がり、しこりなどです。また、ただれや潰瘍ができるケースもあります。
有棘細胞がんは日光角化症が進行して生じたがんと考えられており、日光角化症を治療せず放置すると、有棘細胞がんに至る場合があります。
日光角化症は表皮内に留まるため、転移のおそれはないとされています。しかし、有棘細胞がんに進行してしまうと、がんが血流を介して身体全体に転移するリスクが高まると考えられます。
基底細胞がん
基底細胞がんは、表皮の最下層にある基底細胞や、皮膚の内側で毛根を包んでいる毛包にできるがんです。
初期段階では直径1mmから2mmほどの黒い点が皮膚の表面に現れ、進行すると数個の黒い点が集まり、円形や楕円形に広がります(※2)。さらに進行すると、皮膚がただれてしまい、潰瘍(かいよう)のような状態になります。
なお、基底細胞がんは、表皮内に留まる特性があるため、体内の他の部位に転移することは少ないとされています。
メラノーマ
紫外線を原因とする皮膚がんのうち、最も危険性が高いとされているのがメラノーマです。
メラノサイトという皮膚の色素細胞や、ほくろの細胞(母斑細胞)が悪性化してできます。メラノーマは進行が早く、かつ悪性度の高い皮膚がんのため、進行すると命を落とすリスクもあるといわれています(※3)。
また、メラノーマは日本人より白人の罹患率が高く、近年では欧米スタイルの生活の変化などにより、日本人の罹患率も増加傾向とされています(※4)。
紫外線による皮膚がんを防ぐには

紫外線による皮膚がんを防ぐには、紫外線を浴びない生活を心がけることが重要です。ここでは、簡単にできる紫外線対策をお伝えします。
外出は紫外線の強い時間帯を避ける
紫外線量は時間帯によって異なるため、外出は強い時間帯を避けましょう。朝の10時頃から次第に紫外線が強くなり、正午前後にピークを迎え、15時を過ぎると急速に弱まります(※1)。
気象庁では、日本全国の紫外線の強さが一目でわかるを紫外線情報(分布図)公開しています。リアルタイムの紫外線の強さや量だけではなく、翌日の予測も確認できるため、ぜひ外出時間の参考にしてください。
外出時には日傘や帽子を利用する
紫外線の強い時間帯に外出せざるを得ないときは、日傘や帽子を活用しましょう。帽子や日傘は、直射日光から身体を守ってくれます。また、最近では紫外線防止機能が備わった商品も販売されているので、それらを有効活用するのもおすすめです。
ただし、日傘や帽子は直射日光からの紫外線をある程度防げますが、地面や建物から反射した紫外線、大気中に散乱した紫外線までは完全にカバーしていない点に注意しましょう。
身体を覆う部分が多い衣服を着る
首や腕、肩などを紫外線から守るためには、袖が長い襟つきのシャツなどといった身体を広範囲で覆う衣服の着用をおすすめします。紫外線から皮膚を守るためには、生地選びも重要です。紫外線対策としておすすめなのは、織り目や編み目が詰まっている生地です。
ただし、織り目や編み目が細かい生地は、通気性や吸湿性がやや劣るとされています。熱中症のリスクが高まる夏場には、無理のない範囲で着用する服を選びましょう。
日焼け止めを使う
顔など衣服では覆えない場所の紫外線対策としては、日焼け止めの使用が有効です。日焼け止めは、リキッド(液状)、乳液、クリーム、ジェル、スティック、スプレー、シートなど、さまざまなタイプが販売されています。いずれの種類にも、酸化亜鉛、酸化チタン、メトキシケイヒ酸オクチルといった紫外線防止剤が入っています。
紫外線防止剤は、紫外線散乱剤と紫外線吸収剤の2つに分類されます(※5)。
紫外線散乱剤でアレルギーを起こすことはほぼないとされていますが、紫外線吸収剤はまれにアレルギー反応を示す方がいると考えられているため、注意が必要です。
敏感肌の方は「紫外線吸収剤無配合」「紫外線吸収剤フリー」「ノンケミカルサンスクリーン」といった表示がされている商品をおすすめします。
紫外線は浴びすぎないことが重要!適度な日光浴は健康維持に有効

日焼けによる皮膚がんを防ぐためには、日焼けをなるべく避ける対策が不可欠です。特に若いうちからの過度な日焼けは、年齢を重ねると皮膚がんのリスクを高めるとされています。
とはいえ、「日光浴」という言葉もあるように、日光には健康効果があることも事実です。適度な日光浴は、ビタミンDの生成や、セロトニンの分泌を促します。紫外線対策をしつつ、適度な日光浴で健康を維持するよう心がけましょう。
(※1)環境省|紫外線環境保健マニュアル2020
(※2)国立研究開発法人国立がん研究センター |基底細胞がん
(※3)がん研有明病院|皮膚腫瘍科
(※4)国立がん研究センター 希少がんセンター|悪性黒色腫(メラノーマ)
(※5)環境省|紫外線による 影響を防ぐためには