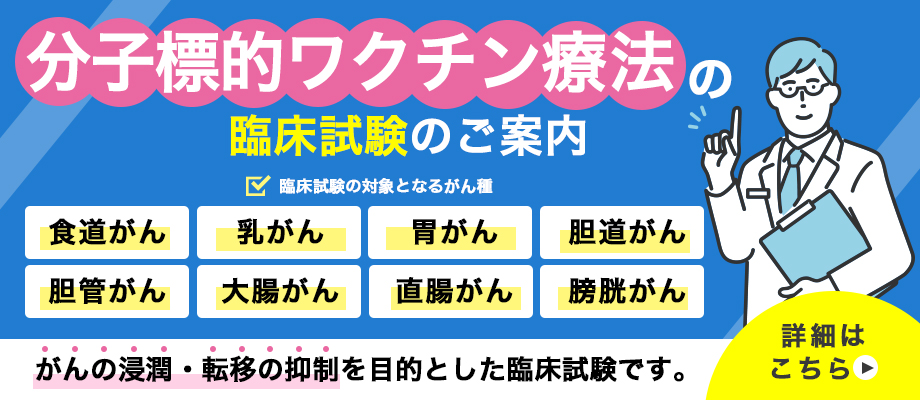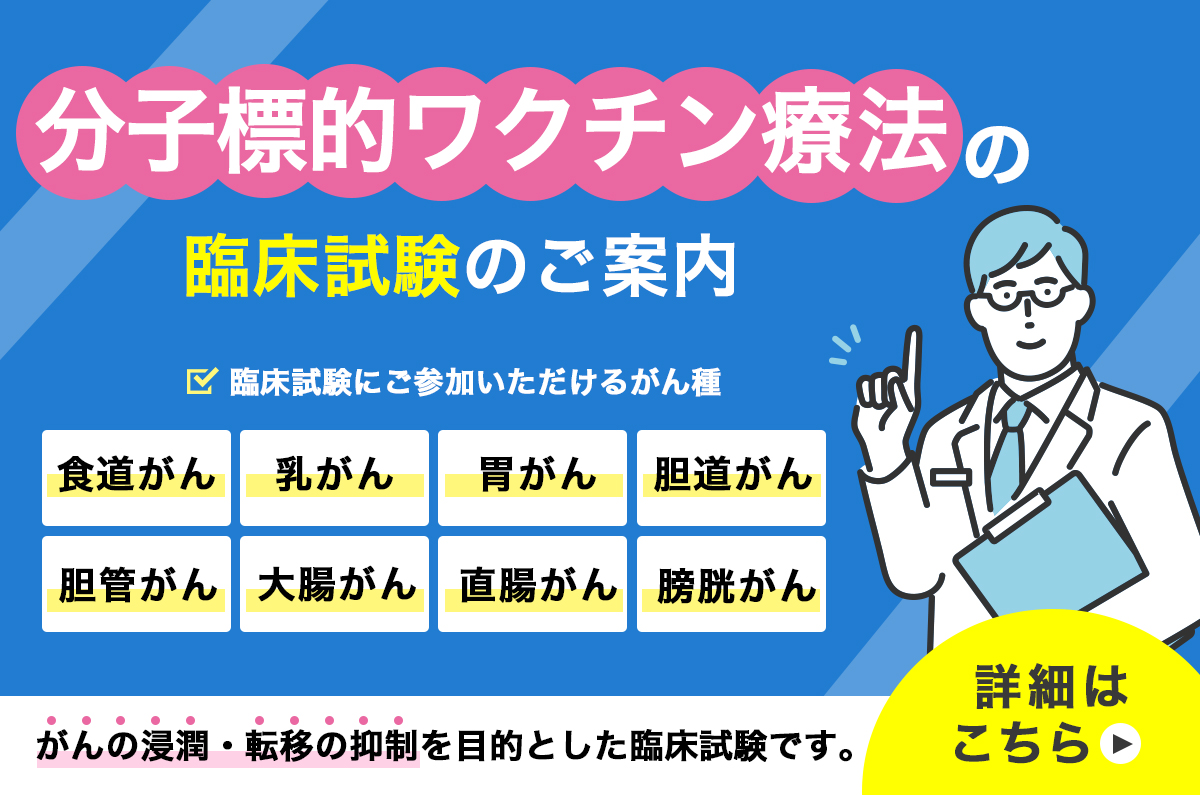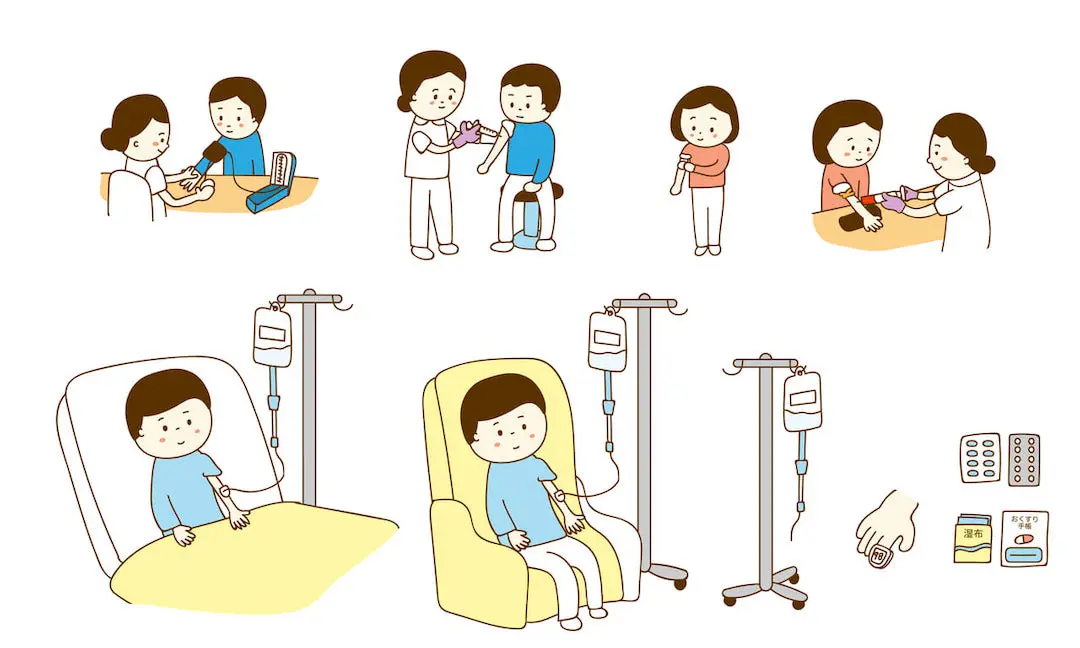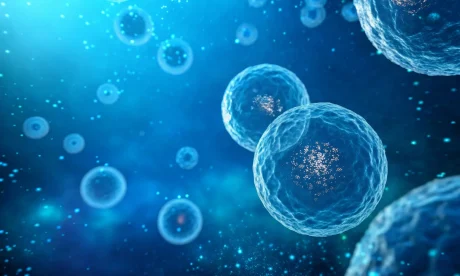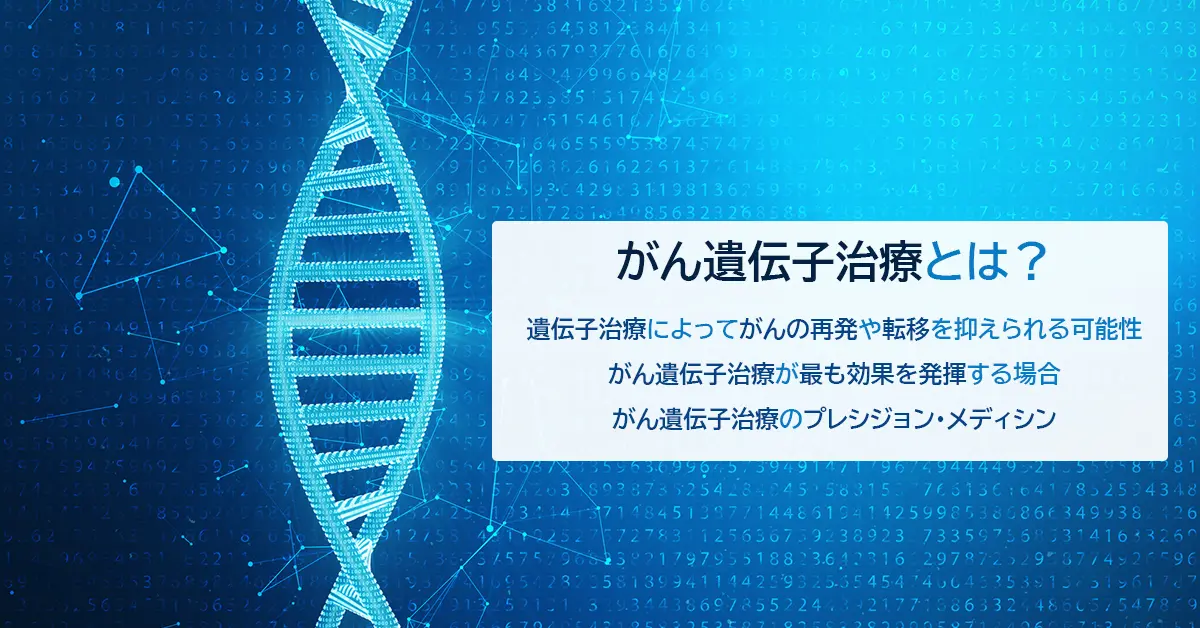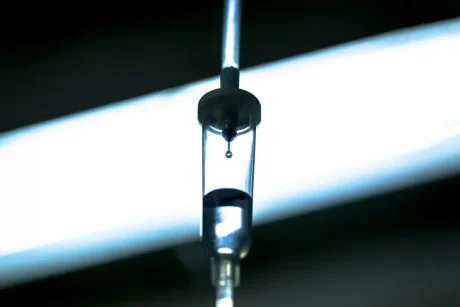腎臓がんになった場合、最も基本的な治療法は手術です。 腎臓を摘出した後は、日常生活にどのような影響を及ぼすのか気になる方も少なくありません。
この記事では、気になる腎臓摘出後の後遺症や食事制限、仕事復帰について詳しく解説します。注意すべき症状についてもまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
腎臓摘出後の生活はどうなる?まず知っておきたいこと
腎臓摘出後の生活はどのように変わり、何に気をつけて過ごせばよいのでしょうか。まずは知っておきたい基本的な情報について、具体的に解説していきます。
片方の腎臓を失っても生活できる?
腎臓は左右に一つずつあり、片方の腎臓を摘出しても、残った腎臓が健康であれば多くの場合、生活に大きな支障はありません。 残った腎臓が機能を補い、老廃物の排出や水分や電解質のバランスを保つためです。
ただし、術後しばらくは疲れやすさやむくみ、血圧の変動が見られる場合があります。塩分の摂りすぎや脱水は腎臓に負担をかけるため、体調の変化に注意しましょう。定期的な血液・尿検査を行い、生活習慣を整えれば、多くの方が術前と変わらずに日常を送れます。
術後の痛みの経過
腎臓摘出後は、治癒までの間に皮膚や筋肉の痛みを伴う場合があります。 痛みの程度や期間には個人差がありますが、通常は数日から2週間程度で落ち着くでしょう。ただし、場合によっては数カ月間続くため、痛みの変化を観察しながら過ごしてください。
術後に見られる痛みと治まるまでの日数の目安は、以下の通りです。
- 創部に由来する鋭い体性痛:術後1〜2週間
- 腹部の鈍い内臓痛:術後〜数日
- 腹腔鏡手術で生じやすい肩への放散痛:術後数時間〜数日
- 神経障害性疼痛:まれに術後数カ月間続く
痛みが急に強くなったり、発熱を伴ったり、長期間続いたりする場合は、早めに主治医へ相談しましょう。
摘出後の後遺症リスクと経過観察の重要性
腎臓摘出後は、手術による傷や肩の痛みなど、一時的な後遺症が現れる場合があります。 中には、しばらく違和感やしびれが続く方もいます。また、腎機能の低下や慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)といった後遺症につながる可能性があるため、定期的な血液・尿・画像検査を受けることが必要です。
さらに、腎臓がんは10年以上経過してから再発する例もあり、長期的な経過観察が欠かせません。 術後は日常生活への復帰を焦らず、少しでも気になる症状があれば、早期に医師へ相談しましょう。適切な治療や生活管理を行うことが重要です。
まれに透析が必要になるケースもある
腎臓を摘出すると、残った腎臓にどうしても負担がかかります。そのため、血液検査や尿検査で腎機能の低下が生じている、または高血圧や糖尿病など腎臓に負荷をかける疾患のある方は、注意が必要です。残った臓器に負荷がかかり働きが徐々に弱まると、透析が必要になるケースもあります。
透析は、血液や腹膜を使用して老廃物や余分な水分を取り除く治療です。定期的な通院が必要となり、生活への影響が大きくなります。腎臓摘出後は腎機能の維持に気を配ることが重要です。定期的な血液・尿検査で状態を確認しつつ、日常生活で塩分や水分を控えるなどの工夫を行い、後遺症の発生を防ぎましょう。
腎臓摘出後の食事制限と生活習慣

腎臓摘出後は残った腎臓に負担をかけやすいため、適切な食事制限と生活習慣が何よりも重要です。初期時の基本や運動・睡眠・禁煙習慣、飲酒について詳しく解説します。
食事の基本と塩分・水分管理のポイント
腎臓摘出後は、残った腎臓への負担を減らすため、食事と水分管理に注意してください。塩分は1日6g未満を目安にし、加工食品や外食を減らしましょう(※1) 。
腎臓で処理する栄養素として、タンパク質・リン・カリウムがあります。腎機能が保たれている場合、原則として制限は不要です。しかし、腎機能低下がある場合は、高タンパク食、生野菜や果物の過剰摂取、リンを含む加工食品は控える必要があります。
水分は、多すぎても少なすぎても腎機能に負担がかかります。基礎疾患や体格、季節で適量は変わるため、医師の指示を優先しながら調整しましょう。夏場の暑い時期や下痢をしているときは、意識的な水分補給をすることが必要です。
運動・睡眠・禁煙習慣
運動は術後の回復状況を踏まえたうえで、必ず医師の許可を得てから始めましょう。ウォーキングなど軽度の有酸素運動は、高血圧や肥満に効果的とされており、残った腎臓の維持にも役立ちます。体調に合わせて、無理のない範囲で継続しましょう。
また、睡眠は腎臓の回復や免疫の維持に欠かせません。疲労や腎臓への負担を減らすために、就寝時間を一定に保ち、十分な休息を取ることが大切です。また、喫煙は腎機能低下のリスクを高めるため、術後は禁煙を徹底しましょう。生活習慣の見直しが長期的な健康維持につながります。
飲酒・アルコールとの付き合い方
術後1カ月程度経過し、医師の許可が下りた後に適度な飲酒が可能になるケースが一般的です。 ただし、過度な飲酒は脱水や高血圧を引き起こし、腎機能の低下を早める可能性があります。飲酒する場合は、日本酒なら1合(約180ml)・ビールなら500ml程度 の適量にとどめ、週2日間は休肝日を設けて腎臓を休ませましょう(※2) 。
また、アルコールは利尿作用があるため、体内の水分を失いやすくなります。飲酒の際には適度な水分補給を心がけることが大切です。このような工夫を日常生活に取り入れることで、残った腎臓への負担を軽減しながら、長期的な健康を維持しましょう。
腎臓摘出後の仕事復帰

術後どのくらいの期間で仕事復帰が可能になるのか、気になる方は多いでしょう。基本的には、状況に応じて医師に相談する必要があります。ここでは、腎臓を摘出後の注意したいポイントについて詳しく解説します。
仕事復帰までの目安と注意点
腎臓摘出後の仕事復帰時期は、手術方法や体力の回復状況によって異なります。一般的には、2~3週間程度が自宅静養の目安とされています(※3) 。
無理な復帰は疲労や腎機能への負担を高めるため、手術を担当した医師や産業医の判断を仰ぎましょう。復帰時は短時間勤務や軽作業から始め、徐々に業務量を増やします。在宅勤務や時短勤務、こまめな休憩を組み合わせる方法も、体力を維持しながら働けるのでおすすめです。
体調を管理しながら勤務を続ける
復帰後は、残った腎臓に負担をかけない生活管理が重要です。定期通院や必要であれば服薬を行いながら体調に応じた働き方を選択しましょう。長時間のデスクワークでは、1〜2時間ごとに立ち上がって血流を良くしたり、残業や休日出勤を控えめにして、業務でのストレスや過労をできるだけ抑えるなどの工夫が大切です。
定期的な体調確認を行い、むくみ・倦怠感・血圧変動などの変化があれば、早めに医師へ相談してください。高血圧や糖尿病、高尿酸血症の管理が、腎機能保持のために何よりも重要です。
腎臓摘出後に注意すべき症状と退院後の受診タイミング

腎臓摘出後は出血や尿もれ、感染症、腸閉塞、肺塞栓症などの合併症に注意が必要です。次の症状があれば、放置せず速やかに受診しましょう。
- 発熱
- 血尿
- 背中や腹部の痛み
これらの症状は、合併症や再出血のサインを示している可能性があります。
また、術後しばらくは傷の部分に負荷がかかる「体幹をねじる」「重い物を持つ」などの動きを控えましょう。術後は炎症のために血栓ができやすいため、こまめな歩行や水分摂取も大切です。症状がない場合も定期的な診察を受け、回復状況や腎機能を確認しながら過ごしましょう。
腎臓摘出後に不安を感じたら専門家に相談を

腎臓摘出後は多くの場合、後遺症を発症することなく、日常生活へと戻れるケースがほとんどです。しかし、術後しばらくは食事制限や仕事復帰などさまざまな配慮が必要です。自己判断で進めてしまうと、かえって体調を崩す原因になるため注意しましょう。
少しでも体調面や生活面での不安を感じたら、早めに医療機関を受診してください。定期検診や医師からのアドバイスを受けながら、腎臓摘出後も健康的に過ごすことが重要です。
(※1)厚生労働省|ナトリウム(食塩)とカリウムを測って健康に – ナトカリ手帳
(※2)厚生労働省|アルコール
(※3)国立がん研究センター|肝臓がんロボット支援手術を受けるみなさまへ