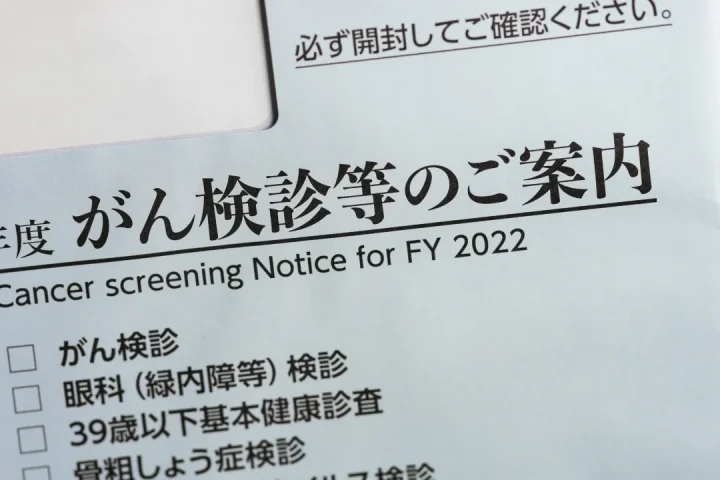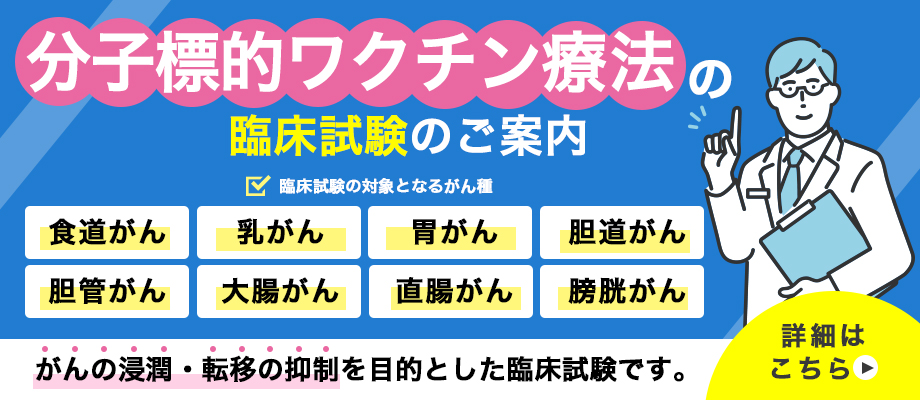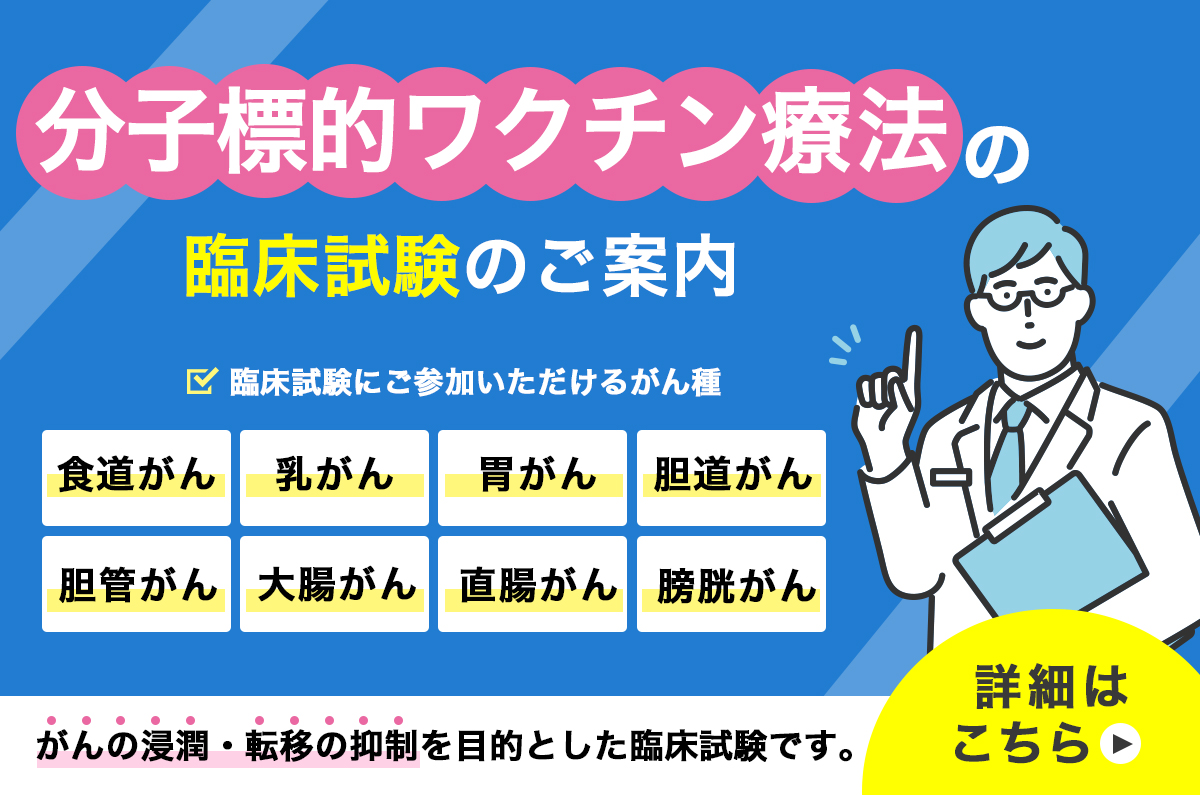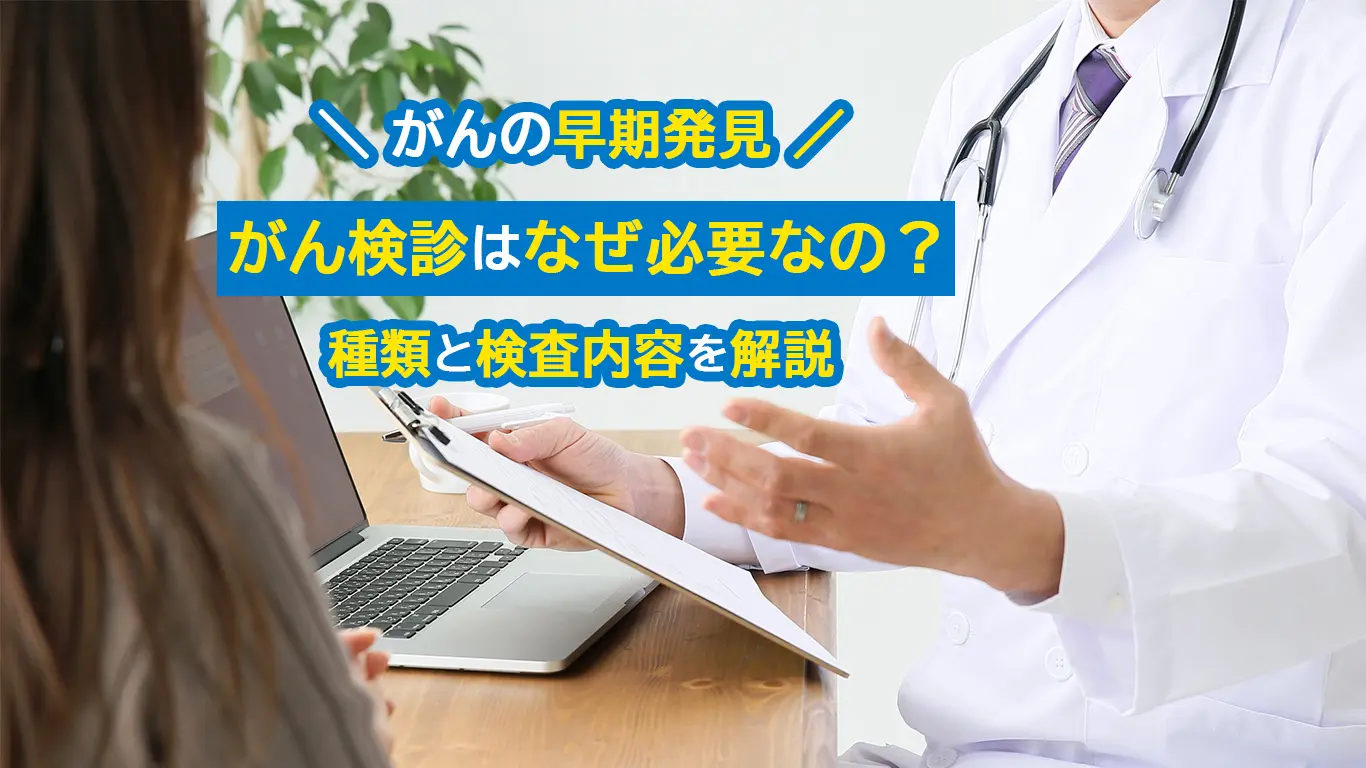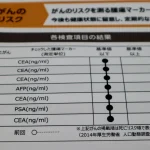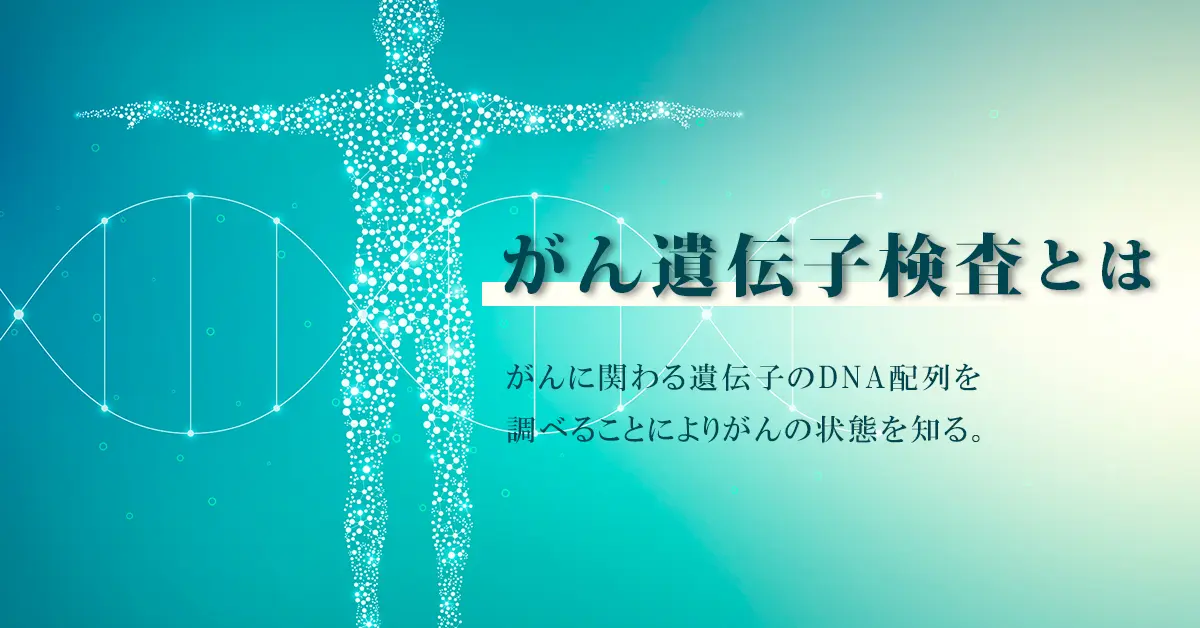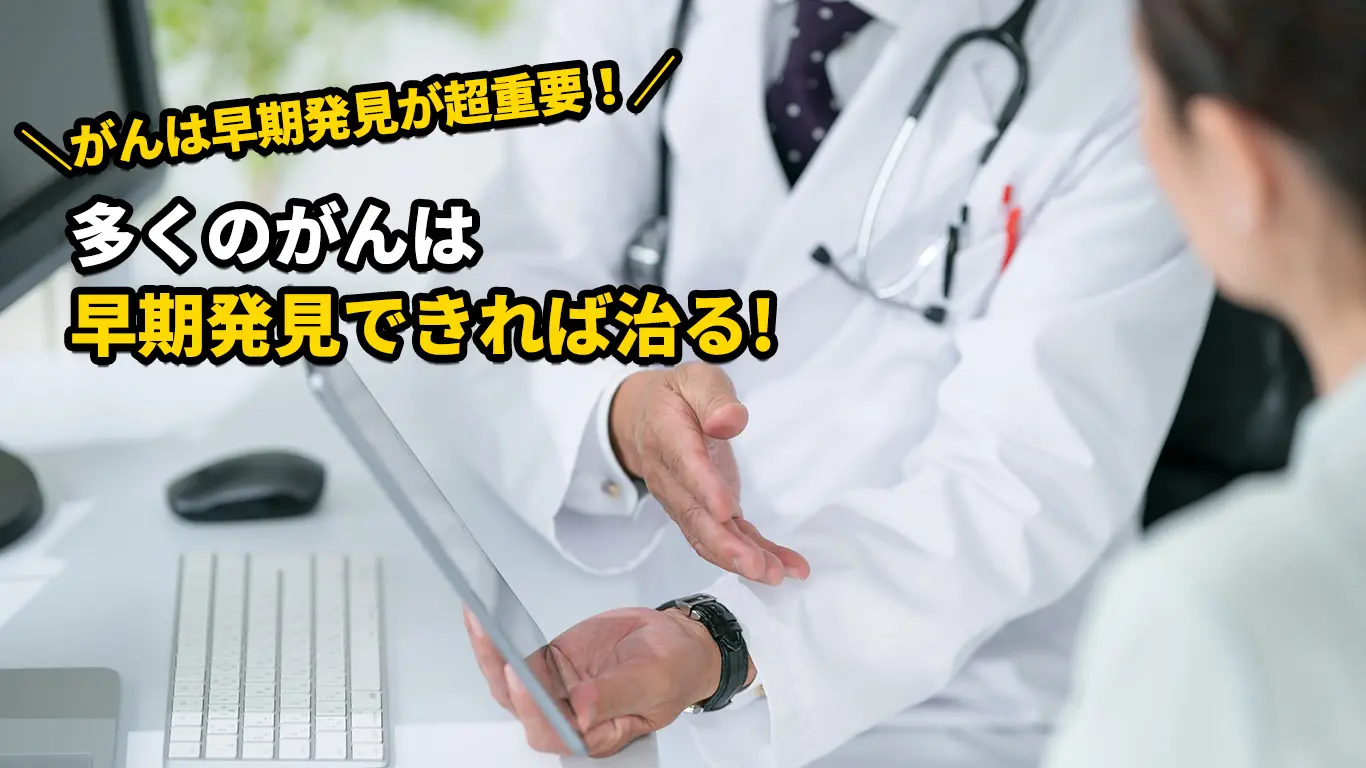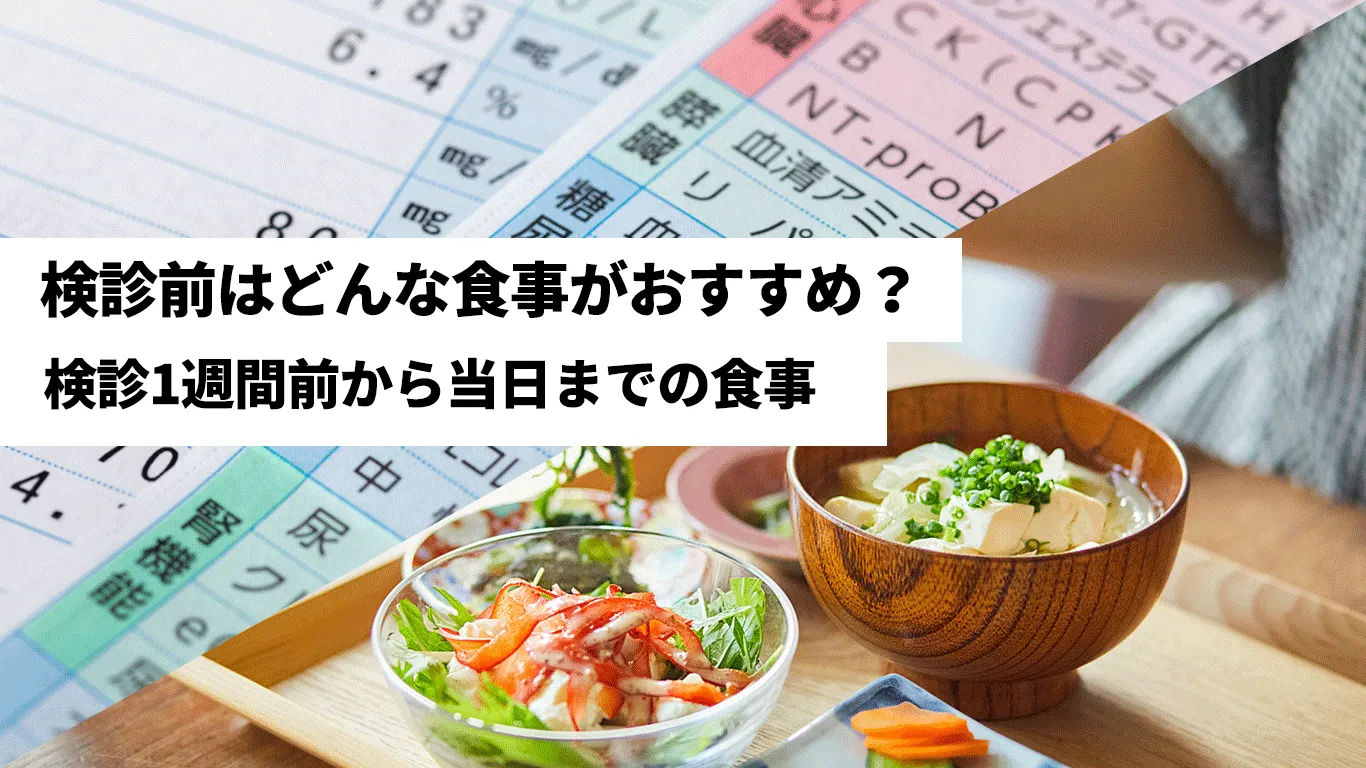年齢を重ねていく中で、がん検診の適切な頻度について気になり始めた方もいるのではないでしょうか。
本記事では、がん検診別の対象年齢や検査項目、検診の注意事項や判定後の流れについて解説します。それぞれの検診の内容を把握し、適切なタイミングで検診を受けることで、健康管理につなげましょう。
目次
がん検診の適切な頻度

厚生労働省では、がん検診の受診率を60%以上にすることを目標として、以下のがん検診の受診を推進しています(※1)。自分自身の年齢を踏まえ、適切な検診を受診してください。
胃がん検診
胃がんは国内のがんによる死亡原因の上位に位置し、患者数は50代以降で増加すると考えられています(※2)。胃がん検診の対象年齢と検査項目は、以下の通りです。
対象年齢と受診頻度
胃がん検診は、50歳から2年に1度の頻度で定期的に受診を推進しています(※2)。
検査項目
胃がん検診で実施される検査項目は、以下の通りです。
| 胃がん検診の検査項目 | 検査概要・注意事項 |
|---|---|
| 胃部X線検査 | ・バリウム(造影剤)と発泡剤(胃を膨らませる薬)を飲み、胃の粘膜を観察する検査 ・バリウムによって便秘や腸閉塞を起こすことがまれにある ・過去に当該検査で異常があった方や水分制限を受けている方は医師に相談が必要 |
| 胃内視鏡検査 | ・鼻もしくは口から胃の中に内視鏡を挿入し、胃の内部を観察する検査 ・抗凝固剤を服用している方は受診できない場合がある ・常用薬やアレルギーがある方は医師に相談が必要 |
胃がんの原因や治療法などを詳しく知りたい方は以下の記事を参照し、知識を深めましょう。
子宮頸がん検診
子宮頸がん患者は20歳代後半から増加し始め、特に30代から50代で多くなります(※3)。子宮頸がん検診の対象年齢と検査項目は、以下の通りです。
対象年齢と受診頻度
子宮頸がん検診では、細胞診検査の場合は20歳から2年に1度、HPV検査単独法の場合は30歳から5年に1度の頻度で定期的に受診しましょう(※3)。
検査項目
子宮頸がん検診で実施される検査項目は、以下の通りです。
| 子宮頸がん検診の検査項目 | 検査概要・注意事項 |
|---|---|
| 細胞診検査 | ・医師が子宮頸部(子宮の入り口)を専用のヘラやブラシでこすって細胞を採取し、異常な細胞がないかを顕微鏡で調べる検査 |
| HPV検査単独法 | ・医師が子宮頸部(子宮の入り口)を専用のヘラやブラシでこすって細胞を採取し、HPV感染の有無を調べる検査 |
子宮頸がんの原因や治療法などを詳しく知りたい方は以下の記事を確認し、理解を深めてください。
肺がん検診
肺がんは国内のがんによる死亡原因の上位に位置し、患者数は40代以降で増加すると考えられています(※4)。肺がん検診の対象年齢と検査項目は、以下の通りです。
対象年齢と受診頻度
肺がん検診は、40歳から1年に1度の頻度で定期的に受診しましょう(※4)。
検査項目
肺がん検診で実施される検査項目は、以下の通りです。
| 肺がん検診の検査項目 | 検査概要・注意事項 |
|---|---|
| 胸部X線検査 | ・胸のX線撮影を実施する検査 ・胸部全体を写すために、大きく息を吸い込み、しばらく止めて撮影する ・現時点、検査による放射線被ばくによる健康被害はほとんどないとされる (※2025年1月時点) |
| 喀痰細胞診 | ・たばこを頻回に吸う人に対して、喫煙との関連が大きいがんを発見するために実施する検査 ・3日間起床時に痰(たん)を採取し、痰に含まれる細胞を調べる。 |
肺がんの原因や治療法などを詳しく知りたい方は次の記事を確認しましょう。
肺がんとは
乳がん検診
乳がんは国内のがんによる死亡原因の上位に位置し、患者数は30代後半以降で増加し、40歳以上の女性では最も罹患する方が多いとされています(※5)。乳がん検診の対象年齢と検査項目は、以下の通りです。
対象年齢と受診頻度
乳がん検診は、40歳から2年に1度の頻度で定期的に受診しましょう(※5)。
検査項目
乳がん検診で実施される検査項目は、以下の通りです。
| 乳がん検診の検査項目 | 検査概要・注意事項 |
|---|---|
| マンモグラフィ検査 | ・胸のX線撮影を実施する検査 ・乳房を片方ずつプラスチックの板で挟んで撮影し、小さいしこりや石灰化を発見するための乳房専用のX線検査 ・圧迫時間は数十秒程度であるものの、痛みを感じることがある ・現時点、放射線被ばくによる健康被害はほとんどないとされる (※2025年1月時点) |
乳がんの原因や治療法などを詳しく知りたい方は以下をご覧いただき、理解を深めましょう。
大腸がん検診
大腸がんは国内のがんによる死亡原因の上位に位置し、患者数は40代以降で増加すると考えられています(※6)。大腸がん検診の対象年齢と検査項目は、以下の通りです。
対象年齢と受診頻度
大腸がん検診は、40歳から1年に1度の頻度で定期的に受診しましょう(※6)。
検査項目
大腸がん検診で実施される検査項目は、以下の通りです。
| 大腸がん検診の検査項目 | 検査概要・注意事項 |
|---|---|
| 便潜血検査(2日法) | ・2日分の便を採取し、便に混じった血液を検出する検査 ・ポリープやがんなどの大腸疾患があると大腸内に出血することがあるため、それを想定し血液を検出する。 |
大腸がんの原因や治療法などを詳しく知りたい方は以下の記事を参照し、知識を深めましょう。
がん検診の判定後の流れ
がん検診後、「がんの疑いなし(精密検査不要)」だった場合は問題ありませんが、次回の検診を受けるまでの間で突発的に大きくなるがんもあります。そのため、何か気になる症状が現れた場合は、次回の検診を待たず速やかに医療機関を受診しましょう。
「がんの疑いあり(要精密検査)」だった場合は、必ず速やかに医療機関で精密検査を受けてください。要精密検査と判定されたとしても、必ずがんであるとは限りません。しかし、放置すると、がんだった場合に診断が遅れ、進行してしまうリスクがあります。
取り返しのつかない事態に発展する前に、必ず医療機関を受診しましょう。
がん検診を受ける際に知っておくべきこと

がん検診を受ける際には、以下のデメリットを把握しておくことが重要です。
偽陰性
・実際にはがんであるのに、精密検査が必要ないと判定されること
・がんの治療が遅れるリスクが発生する
偽陽性
・実際にはがんではないにもかかわらず、がんの疑いあり(要精密検査)と判定されること
・本来受ける必要のない精密検査を受けなければならなくなり、心身に負担がかかる
過剰診断
・命に別状のないがん(成長スピードが極めて遅いといった理由で治療をしなくても問題ないがん)を検診で発見すること
・治療の必要性を判断することが困難なため、不要な治療が発生し、心身ともに負担がかかる
偶発症
・精密検査や検診などの医療行為によって起こる合併症
・例として、バリウムによる誤嚥性肺炎や腸閉塞、内視鏡による出血や穿孔(せんこう)、放射線被ばくなどが挙げられる
がん検診が受けられる検診機関の探し方

がん検診を受ける際は、あらかじめ指定された医療機関を受診する場合がありますが、提示された医療機関リストから自分で選ぶケースもあります。自分で医療機関を探す場合は、ホームページでがん検診に対応しているかを確認してください。
また、かかりつけの医師に相談したり、居住の市区町村で住民検診を実施する施設を探したりするのもおすすめです。自分に合う方法で情報収集し、適切なタイミングでがん検診を受けましょう。
年齢を踏まえ適切な頻度でがん検診を受診しよう
がん検診の適切な頻度は、胃がん検診や子宮頸がん検診、肺がん検診や乳がん検診、大腸がん検診によって異なります。
それぞれの検診における適切なタイミングを踏まえ、定期的に受診しましょう。
また、自分で異変を感じる場合は、速やかに医療機関を受診することが重要です。がんとは無縁の健康的な生活を維持するためにも、定期的に検診を受診し、健康管理を徹底していきましょう。
(※1)厚生労働省|がん検診
(※2)国立研究開発法人国立がん研究センター|胃がん検診について
(※3)国立研究開発法人国立がん研究センター|子宮頸けいがん検診について
(※4)国立研究開発法人国立がん研究センター|肺がん検診について
(※5)国立研究開発法人国立がん研究センター|乳がん検診について
(※6)国立研究開発法人国立がん研究センター|大腸がん検診について
参照日:2024年1月