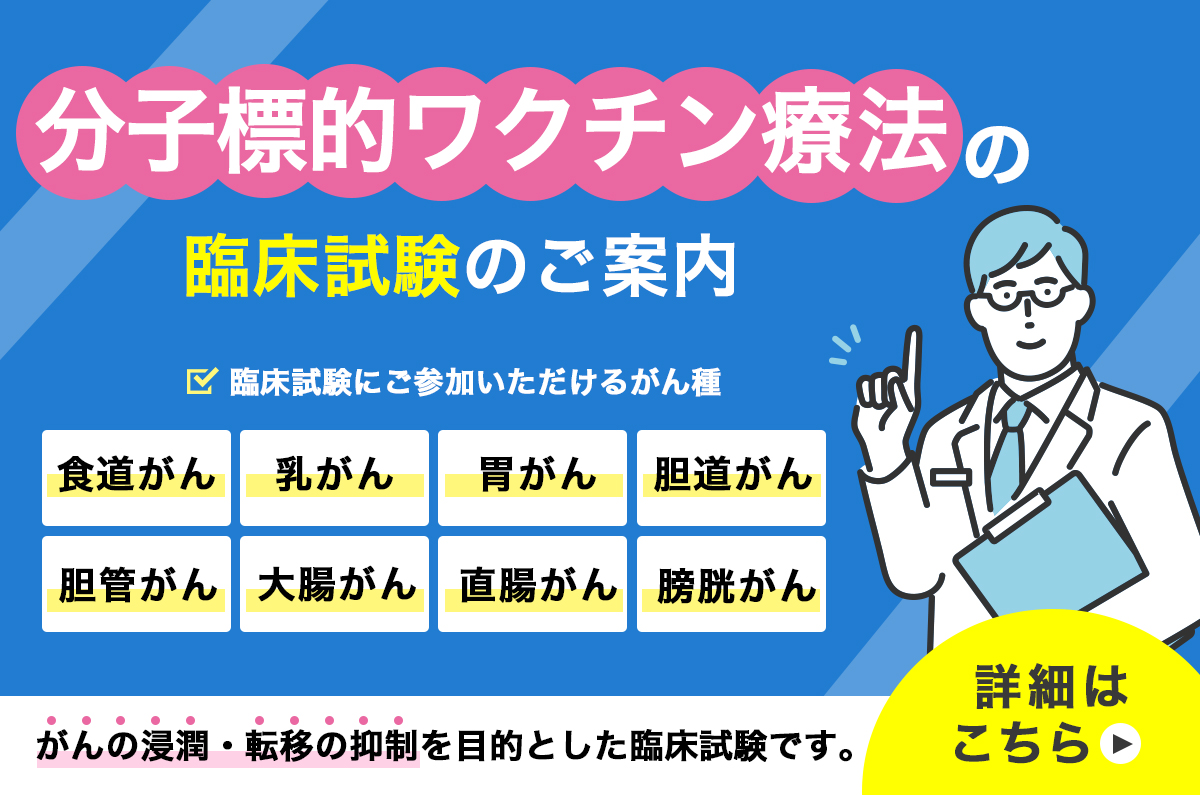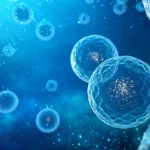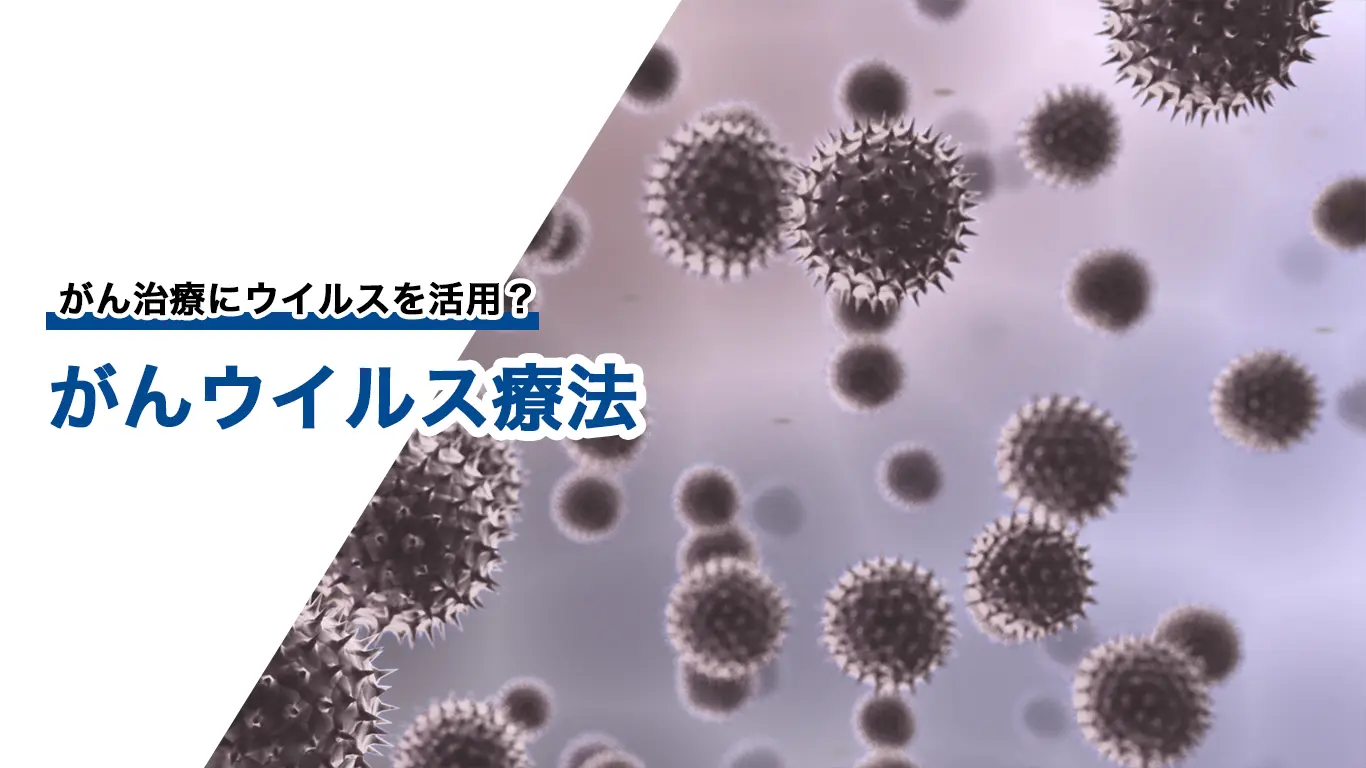ラジオ波焼灼(しょうしゃく)療法は、RFAとも呼ばれ、高周波の電流によってがん(悪性腫瘍)を焼灼する治療法です。特に肝がんの治療に広く用いられ、外科手術が困難な患者さんにも実施されています。
本記事では、ラジオ波焼灼療法の仕組みや適応基準、治療の流れ、メリット・デメリットを解説します。他の治療法についてもご紹介しますので、ご自身に適したがん治療を検討する際の参考にしてください。
目次
ラジオ波焼灼療法(RFA)とは

ラジオ波焼灼療法(RFA:Radiofrequency Ablation)は、肝がんにおける手術や塞栓(そくせん)療法、薬物療法などと並ぶ「穿刺(せんし)局所療法」の一つです。治療の仕組みや適応基準、保険適用の有無を見ていきましょう。
ラジオ波焼灼療法は「穿刺局所療法」の一つ
ラジオ波焼灼療法は、超音波でがんの位置を確認しながら、皮膚から直接がんに直径1.5mmの電極針を刺し、約450kHzの高周波の電流によってがんを焼灼する治療法です(※1)。メスで切開する必要がないため、身体への負担が少なく、入院期間も短期間というのが特徴です。
穿刺局所療法の他の療法として、経皮的エタノール注入療法(PEI)と経皮的マイクロ波凝固療法(PMCT)もあります。ラジオ波焼灼療法は、肝機能の低下により手術が困難な方や高齢の方でも治療に対応できるため、穿刺局所療法の中でも中心的な役割を果たしています。
肝がんにおける適応基準
ラジオ波焼灼療法は、一般的にChild-Pugh(チャイルド・ピュー)分類のAまたはBで、「がんの大きさが3cm以下、かつ、3個以下」の場合に適応となります(※2)。
Child-Pugh分類とは、肝機能の状態を数値化し、その合計した点数によってA・B・Cの3段階に分けた指標です。Aが軽度で、Cに進むにつれて肝障害の程度が重度となります(※3)。医療機関によっては独自の適応基準を設定しており、患者さんの全身状態やがんの進行度を踏まえたうえで最終的に判断されます。
保険適用の有無
ラジオ波焼灼療法は、肝がんの治療で保険適用されます。欧米で1995年頃に開発され、日本で1999年あたりから日本での臨床で導入されました(※4)。2004年4月の診療報酬改定に伴い、日本でも保険が適用され、現在では肝がんの標準治療の一つとして用いられています(※4)。
また、肝がん以外にも、乳がんや肺がん、骨軟部腫瘍など、一部のがんに対しても行われるようになり、保険の適用範囲も広がっています。
ラジオ波焼灼療法の手順・流れ

ラジオ波焼灼療法は、外来受診から入院、治療、退院までの一連の流れがあります。退院後は定期的な経過観察が必要です。順を追って見ていきましょう。
外来受診・治療前検査
ラジオ波焼灼療法の実施前には、外来で医師の診察を受けるのが一般的です。採血やレントゲン、心電図といった基本的な検査に加え、必要に応じてCTやMRI、超音波検査が行われます。医師は、検査の結果をもとに、ラジオ波焼灼療法を行うかを判断し、入院日程を決定します。
入院・治療
多くの場合、入院は治療の数日前から前日に設定されます。治療前日の夜からは、原則として絶食(病院によって異なる場合がある)となり、治療当日は点滴が行われます。
腹部の局所麻酔を行い、超音波で位置を確認しながら電極針を刺し、がんを焼灼します。治療にかかる時間は、がんの状態によって異なりますが、おおむね30分から2時間ほどです(※4)。焼灼の際に痛みを感じることがあるため、鎮痛剤や点滴での麻酔で痛みを和らげながら進めるのが一般的です。治療後は、出血や痛み、感染などの合併症のリスクもあります。看護師が慎重に経過を観察し、医師の許可が下りるまではベッドで安静に過ごすことが大切です。
入院期間と治療後の経過
治療後は、翌日から数日以内にCT検査が行われ、がんの焼灼状況を確認します。問題がなければ、数日後には退院が可能です。もし追加の治療が必要と判断された場合は、再度治療が行われます。
退院後は、約3カ月から4カ月に1回のペースで定期検査のため通院が必要です。肝細胞がん、転移性肝がんは再発リスクが高いため、血液検査やCT、MRIなどを受け、経過を観察し、定期的なフォローアップが不可欠です。
ラジオ波焼灼療法のメリット・デメリットと合併症のリスク
ラジオ波焼灼療法は、身体への負担が少なく、再治療が可能であることが大きなメリットです。一方で、がんの大きさや位置による制限があり、合併症リスクも存在します。メリット・デメリットと合併症のリスクについて見ていきましょう。
ラジオ波焼灼療法のメリット
ラジオ波焼灼療法の最大のメリットは、開腹せず治療できる点です。また、治療効果が不十分な場合でも、数日後には再治療ができます。
通常の入院期間は3〜5日程度と比較的短く、日常生活への復帰も早い傾向です。これらのメリットにより、適応範囲が拡大しています。
ラジオ波焼灼療法のデメリット
ラジオ波焼灼療法にはいくつかのメリットがありますが、全てのがんに適応されるわけではありません。がんの大きさや個数によっては、適さない場合もあります。
前述のとおり、肝がんでは大きさが3cm以内で、かつ3個以内が目安です(※2)。そのため、がんが大きい場合や個数が多い場合は選択されないケースもあります。また、他の臓器に転移がある場合には実施できないこともあります。
合併症のリスク
ラジオ波焼灼療法は、発熱や腹痛、出血、隣接する臓器の損傷といったリスクもあります。治療後は、慎重な経過観察が必要です。もし副作用や合併症が起きた場合には、状況に応じて適切な治療が行われます。身体への負担は他の治療法より低いものの、リスクを理解しておくことも大切です。
肝がんの他の治療法

肝がんの治療法は、手術や塞栓療法、薬物療法などもあります。がんの大きさや個数、肝機能の状態、年齢や全身状態などを総合的に判断して、適切な治療法が選択されます。
手術(肝切除・肝移植)
肝切除は、がんとその周囲の組織を手術によって取り除く治療法です。Child-Pugh分類がAないしはBの場合、がんが肝臓内にとどまっていれば、大きな腫瘍でも切除が可能なことがあります。ただし、患者さんの状態によっては、別の治療法が選択されることが考えられます。
また、Child-Pugh分類Cの場合に推奨されるのは、肝移植です。患者さんの肝臓を摘出し、ドナーから提供された肝臓に置き換える治療です。現在、日本で行われている肝移植には、健康な方の肝臓の一部を提供する「生体肝移植」と、脳死状態のドナーから肝臓の提供を受ける「脳死肝移植」があります。
塞栓療法(TACE/TAE)
TACE(Transcatheter Arterial Chemo-Embolization:肝動脈化学塞栓療法)やTAE(Transcatheter Arterial Embolization:肝動脈塞栓療法)は、カテーテルを用いて肝動脈を詰まらせ、がんへの血流を減らす治療です。ラジオ波焼灼療法が難しい大きながんや、多発性のがんに適応されます。ラジオ波焼灼療法と併用することで、予後や生存率が向上するとの報告もあります。
薬物療法(分子標的薬・免疫チェックポイント阻害薬)
肝がんの薬物療法では、分子標的薬(ソラフェニブ、レンバチニブなど)や免疫チェックポイント阻害薬(トレメリムマブなど)による全身治療が行われます。進行性の肝細胞がんで、肝機能が良好という場合、Child-Pugh分類Aの患者さんが対象となります。
副作用が強く、仕事や家事など日常生活に影響を与えることもあるため、事前に医師に注意点を確認しておくことが重要です。不安がある場合は、医療従事者のサポートを受けましょう。
放射線療法
放射線療法は、手術や穿刺局所療法が難しい場合や、がんが脈管内に広がっている場合に行われることがあります。しかし、多くの場合、標準治療としては確立されていません。
一方で、定位放射線治療や粒子線治療(陽子線・重粒子線)が受けられる場合もあります。治療を受けられる医療機関は限られているため、希望される場合は医師にご相談ください。
がん治療はラジオ波焼灼療法も選択肢の一つラジオ波焼灼療法も選択肢の一つ
ラジオ波焼灼療法は、近年保険適用の範囲も拡大しており、がんの有効な治療法として注目されています。
ただし、がんの種類や大きさ、個数、全身の状態によって適切な治療法は異なります。ご自身に適した方法を選択するためにも、医師と十分に相談することが重要です。セカンドオピニオンとして、がんの無料相談を利用してみるのも、有効な選択肢の一つです。
(※1)東京大学大学院医学系研究科 消化器内科 |ラジオ波焼灼術(RFA)
(※2)国立がん研究センター|肝臓がん(肝細胞がん)治療
(※3)国立がん研究センター|肝がんの治療について
(※4)東京大学医学部附属病院|消化器内科 肝癌治療チーム