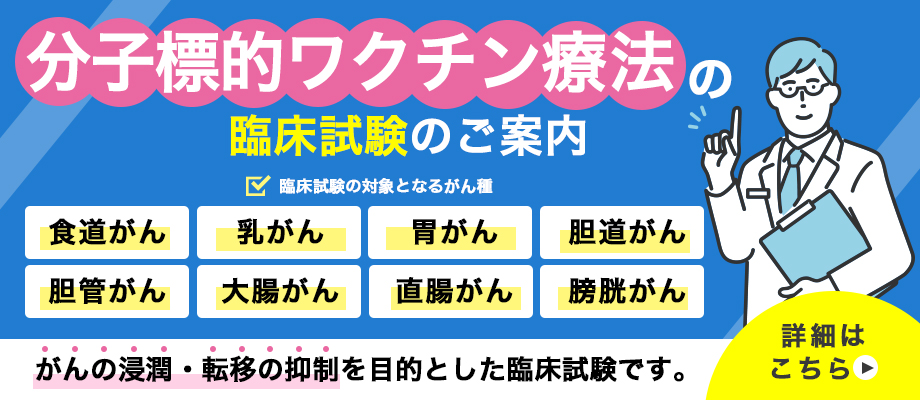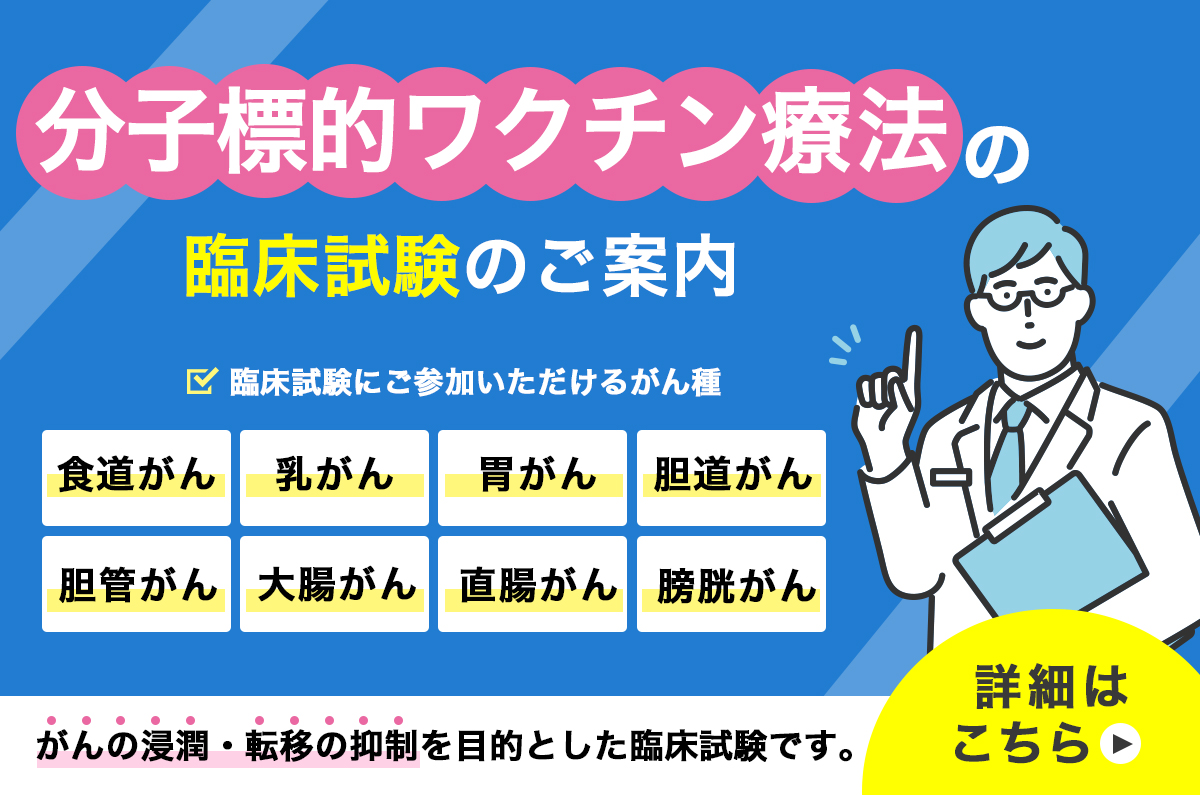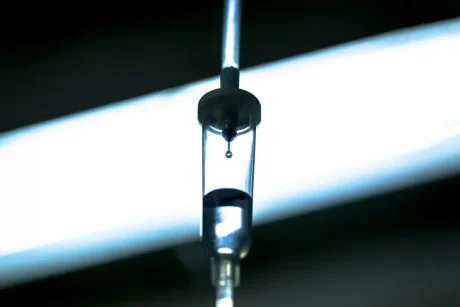脳腫瘍の手術を控え、「後遺症が出てくるのではないか」と不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。脳腫瘍の手術で後遺症が生じるリスクはゼロではありません。そのため、手術前に医師と十分に相談し、理解を深めておくことが大切です。
本記事では、手術後に起こりうる代表的な症状や手術以外の治療法、後遺症と向き合うための方法について解説します。正しい知識を身につけ、ご自身に合った治療法を選択できるようにしましょう。
目次
脳腫瘍の後遺症はあるの?

脳腫瘍の手術後には、腫瘍の位置や種類によって後遺症が現れる可能性があります。ただし、程度には個人差があり、症状がほとんどない場合もあれば、長期間にわたり影響が及ぶこともあります。ここでは、手術による後遺症が生じる主な原因とリスクを見ていきましょう。
手術による後遺症の主な原因は周辺組織へのダメージ
脳腫瘍の手術では、腫瘍を摘出する際に周囲の正常な組織へダメージが及ぶことがあります。重要な神経や血管の近くにある場合や、腫瘍が大きい場合は、後遺症のリスクが高まります。
また、手術中の出血や炎症に伴う脳のむくみ(脳浮腫)も要因になりやすいのです。こうした要因が重なると、手術後に症状が現れる可能性があります。
脳腫瘍の手術による後遺症のリスク
後遺症が現れるかどうかは、腫瘍の種類や部位、大きさ、患者さんの状態によって異なります。
近年は医療技術の進化によって、リスクの低減が可能となっています。例えば、術中ナビゲーションシステムやモニタリングを用いて、脳の状態を確認しながら手術を行う場合などです。とはいえ、リスクを完全に避けることはできません。手術前に十分な説明を受け、納得したうえで手術に臨むことが大切です。
脳腫瘍の手術後に見られる代表的な後遺症

手術で腫瘍を除去した後には、運動機能障害や高次脳機能障害、視力・視野障害、てんかんなどが起こる場合もあります。症状を詳しく見ていきましょう。
運動機能障害
脳腫瘍の手術後には、半身麻痺や運動失調といった運動機能障害が現れる場合があります。特に脳の運動野や小脳に腫瘍があったケースでは、歩行や手足の動きに支障が出ることも少なくありません。症状の程度には個人差がありますが、理学療法や作業療法などのリハビリによって運動機能の改善も期待できます。社会復帰に向けては、専門職による支援を受けることが推奨されます。
高次脳機能障害(言語障害・注意障害・遂行機能障害など)
高次脳機能障害とは、脳の損傷によって生じる認知障害の総称です。記憶力や注意力、言語機能、遂行機能に影響が現れることもあります。
会話がかみ合わなくなる、箸やスプーンの使い方がわからなくなるなどの症状が現れ、日常生活に支障をきたします。外見ではわかりにくいため、周囲からは理解されにくく、生活での困難を招くケースも少なくありません。生活の質を維持するには、症状に応じたリハビリや専門職のサポートが不可欠です。回復には長い期間を要するケースもあり、病院の退院後も支援が求められます。
視力・視野障害
腫瘍摘出後に、視力・視野障害が現れることがあります。 視神経や視交叉の圧迫、損傷を受けた場合は、視野の一部が見えにくくなる「視野欠損」や物が二重に見える「複視」を生じることもあります。日常生活に困難が生じやすいため、リハビリや生活の工夫、安全面への配慮が重要です。
てんかん(けいれん)発作
けいれん発作は、脳腫瘍やその周囲にダメージが生じた場合に見られる後遺症の一つです。症状はさまざまで、けいれん発作を繰り返す「てんかん」を合併するケースも少なくありません。
2020~2022年の間に行われた研究では、「低悪性度神経膠腫と前頭葉にできた腫瘍は、手術後の発作リスクを高める」と報告されています。 また、手術後に一時的に生じる脳のむくみも発作の原因となることがあります。
脳腫瘍の手術以外の治療法
脳腫瘍の治療は、腫瘍の種類やグレード(悪性度)、本人の希望や体調などから判断し、決定されるのが一般的です。
手術以外には、放射線療法や薬物療法、緩和ケアといった治療法があります。
腫瘍の状態によっては、定期的に検査を行い経過観察するケースもあります。治療は、妊孕性(にんようせい:妊娠する力)に影響を及ぼす場合もあるため、将来子どもを望む場合は、治療開始前に妊孕性の温存について医師に相談することが大切です。
放射線療法
放射線療法は、高エネルギーの放射線を照射して、腫瘍細胞を破壊したり、増殖を抑えたりする治療です。
リニアックやサイバーナイフ、ガンマナイフといった装置が使用されます。できるだけ腫瘍部分にのみ放射線を照射し、正常な組織への影響が最小限になるように配慮されます。脳全体を照射する「全脳照射」と、ピンポイントで照射する「定位照射」から選択されるのが特徴です。
薬物療法
薬物療法は、薬を用いて腫瘍を治療したり、症状の軽減を図ったりする治療です。
単独で行う場合もありますが、手術や放射線療法と組み合わせるケースもあります。主な投与方法は、静脈点滴や注射、内服です。また、治療法は、「化学療法」「内分泌療法(ホルモン療法)」「分子標的療法」「免疫療法」の4つに分類されます。腫瘍の種類に応じて、以下の薬が用いられます。
| 種類 | 作用 |
|---|---|
| 細胞障害性抗がん薬 | 細胞分裂を阻害し、がん細胞を攻撃する |
| 分子標的薬 | がん細胞の増殖に関わる分子の働きを抑える |
| 内分泌療法薬(ホルモン療法薬) | ホルモン分泌や作用を抑える |
| 免疫チェックポイント阻害剤 | 免疫細胞の働きを回復し、がんを攻撃できるようにする |
緩和ケア
緩和ケアは、がんに伴う痛みだけでなく、精神的・社会的な辛さやストレスにも対応する包括的なケアです。
脳腫瘍では、身体症状に加えて認知機能の低下や感情面の不安定さを伴うこともあり、診断時からの早い段階からの導入が望ましいとされています。医師・看護師・臨床心理士・医療ソーシャルワーカーといった専門職が連携し、チームで支援します。仕事や家庭、将来の不安などに向き合いながら、今後の生活を考えていくのが大切です。
脳腫瘍と向き合うための方法

手術や治療後には、身体面の後遺症や精神的な不安、社会復帰のことなど、さまざまな問題が生じる可能性が考えられます。そのため、機能の回復や向上には、リハビリテーションや周囲のサポート、定期的な通院が必要です。ここでは、脳腫瘍と向き合う主な方法について見ていきましょう。
1.リハビリテーションの継続と生活の工夫をする
脳腫瘍の手術後に生じる、運動機能障害や高次脳機能障害には、リハビリテーションが効果的です。
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの専門職によるサポートを受けましょう。退院後には、外来リハビリや訪問リハビリを利用するのも一つの方法です。訓練を継続すれば、社会復帰がしやすくなります。また、手すりの設置など住宅環境の整備も重要です。できるだけ早い段階からリハビリに取り組めば、回復の可能性も高まります。
2.周囲のサポートを受ける
脳腫瘍や手術により、認知機能や感情のコントロールが難しくなるケースは少なくありません。高次脳機能障害は外見ではわかりにくく、理解を得るのが難しい場合もあるため、ご家族の負担が大きくなることもあります。
医療ソーシャルワーカーやケアマネジャーなどの専門職に相談し、適切なサービスや支援を受けるのが大切です。その方に合わせて提案してくれるので、一人で抱え込まないようにしましょう。
3.定期的に通院する
脳腫瘍の治療後は、再発や転移の有無を確認するために、定期的に通院するようにしてください。CT検査やMRI検査、血液検査を行い、経過をチェックします。また、治療内容に不安がある場合や、他の選択肢を知りたいときは、セカンドオピニオンも検討しましょう。複数の専門家の意見を聞くことで、納得のいく判断ができるようになります。
後遺症のリスクを減らすために手術前は医師と十分に相談を
脳腫瘍の手術には後遺症のリスクが伴いますが、医療技術の進歩によって、リスクを抑えた手術ができるようになりました。大切なのは、医師や家族と十分に話し合い、自分が納得できる治療法を選択することです。
万が一手術で症状が残った場合でも、適切なリハビリやサポートを受けて生活していくことが大切です。主治医に相談しづらいときには、がんの無料の相談窓口(がん相談支援センター)も活用しましょう。