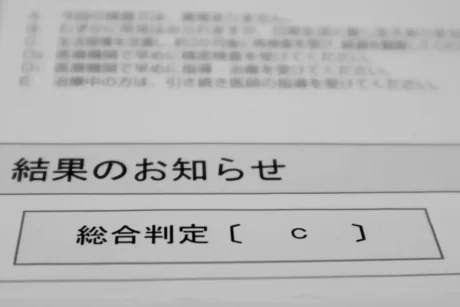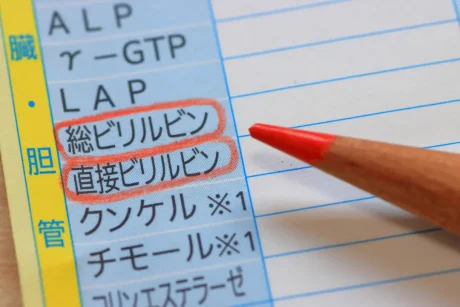50歳を超えると患者が急増する膀胱がん。膀胱は体の中でどんな働きをしていて、膀胱がんはどのような病気なのでしょうか。
ここでは膀胱がんの基本情報と、どういった人に膀胱がんの危険性が高くなるのかについて紹介します。
目次
膀胱がんとは
膀胱がんの種類
膀胱がんは増殖する細胞の種類により分類されます。
- 移行上皮がん
- 膀胱がんで最も多くみられるタイプです。細胞増殖の特徴としては、乳頭状の隆起を作りやすい一方で、膀胱の壁にもぐりこみ始めると早期に転移しやすい傾向があります。
- 扁平上皮がん
- 長期間膀胱に炎症が続くと、膀胱の内側には扁平上皮という細胞が出現します。その細胞ががん化したのものが扁平上皮がんです。
- 腺がん
- 長期の過敏症や炎症の後に発生する腺細胞から発生するがんです。
リスク分類
筋層におよんでいない膀胱がんの治療の基本は尿道から器具を入れ、膀胱の壁を削り取る経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)ですが、TURBTを行った後の追加治療はその後の再発の危険性により分類されたリスク分類によって異なります。
- 低リスク:初回、単発、がんの大きさは3㎝未満、低異型度、0a期
- TURBT後1回だけ抗がん剤の膀胱内注入が行われます。
- 中リスク:低リスクにも高リスクにも該当しない場合
- 抗がん剤の継続的な膀胱内注入やBCG療法を6~8回行います。
- 高リスク:再発、多発性、高異型度もしくは上皮内がん、1期
- BCG療法を6~8回行ないます。場合によってはその後も定期的にBCG療法を行います。膀胱がんは非常に再発の多い病気なので、高リスクと判明した場合には膀胱全摘除術を勧められる場合もあります。
膀胱がんの頻度
2016年にがんと診断された人の中で膀胱がんは男性の第6位(10万人あたり54.4人)、女性の第15位(10万人あたり14.3人)、全体では第6位(10万人あたり33.8人)でした。
また2018年がんで死亡した人の中で膀胱がんは男性の第11位(10万人あたり9.6人)、女性の第13位(10万人あたり4.5人)であり、全体では11位(10万人あたり7.0人)でした。
膀胱がんの主な原因とリスクファクター
タバコ
欧米では以前から喫煙により膀胱がん発症のリスクがあがることが報告されていましたが、日本人を対象にした大規模な報告は近年までありませんでした。2016年に発表された大規模な解析結果では、日本人であっても喫煙は膀胱がんの危険性を2.14倍高めているということが明らかになりました。
喫煙により膀胱がんの危険性が上がる理由としてはタバコに含まれる発がん物質が尿に混じり、膀胱の壁に遺伝子変異を引き起こす機序が考えられています。
カフェイン
タバコの影響を省くため、タバコを吸わない人に限定してコーヒーの摂取量と膀胱がんの発生との関連を調べたところ、男性ではコーヒーを1日1杯以上飲む人は全く飲まない人と比べて2.2倍、膀胱がんになる危険性が見られました。
女性はコーヒーの摂取量では差を認めなかったものの、5杯以上の緑茶を飲む人は膀胱がんの発症リスクが2.3倍になっていました。
これらの調査からカフェインの摂取は膀胱がん発症の危険物質である可能性があります。
染料
染料を作る工程で使用されるナフチルアミン、ベンジジン、アミノビフェニルといった物質には膀胱がんを発生させる危険性があり、実際これらを取り扱う職業の人に膀胱がんの発生が多くみられています。
発がん性が判明してから、これらの薬剤は厳しい条件のもとでしか使用できなくなっていますが、これらの物質に暴露してから膀胱がんを発症するまでには20年以上の潜伏期があると考えられているため、注意が必要です。(これらの物質が原因で発症する職業性膀胱がんの発生は2025年頃までに終息すると考えられています。)
これらの物質による膀胱がんでは、通常の膀胱がんよりも若年で発症する、悪性度が高く、浸潤しやすい、上部尿路の再発の危険性が高いといった特徴があります。
シクロフォスファミド
細胞のDNA合成を阻害する薬で、その特徴を利用して抗がん剤や免疫抑制剤として使用されている薬です。
シクロフォスファミドが体内で代謝されてできるアクロレインという物質が尿から排出されるときに膀胱上皮に障害をきたし、膀胱がんを誘引すると考えられています。
Aristolochia fangchi
漢方薬に使用される広防已の材料となる原植物です。日本の病院で処方可能な防已黄耆湯や疎経活血湯といった漢方薬には防已が含まれていますが、広防已は防已の代わりに使用されることがあります。日本で処方される漢方薬には広防已は使用されていませんが、個人輸入した漢方薬や、中国茶などでは広防已を含むものがあり注意が必要です。
ヒ素
飲料水に含まれるヒ素の濃度と膀胱がんの発生リスクが報告されています。
ミネラルウォータ-のヒ素に関する基準は水道水と比べて緩く設定されており、水道水では1Lあたり0.01mgまで、ミネラルウォータ-では0.05mgまでです。ヒ素は海底や石灰岩の中に多く存在しており、その場所で採取されたミネラルウォーターにはヒ素が水道水よりも濃い濃度で含まれている可能性があります。日本でも土壌にヒ素が多く含まれている地域では膀胱がんによる死亡者が多く見られたとの報告があります。
放射線
骨盤に放射線があたる治療を受けた人では、膀胱がんの発生率が上がると考えられています。
糖尿病
糖尿病の患者は一般の人と比較して1.24倍膀胱がんになりやすかったと報告されています。インスリンをうまく利用できない2型糖尿病では、高血糖や高インスリン血症ががんの発生を促すと考えられています。
機械的刺激
膀胱に物が当たったり擦れたりといった機械的刺激を与えることで、扁平上皮がんタイプの膀胱がんが発生しやすいと考えられています。機械的刺激の原因には、長期間の膀胱留置カテーテルや、膀胱結石などがあります。
そのほかにアフリカや中東地域に生息するビルハルツ住血吸虫という寄生虫は膀胱に寄生し、持続的に炎症を起こすことで扁平上皮がんタイプの膀胱がんの原因になることがわかっています。
ピオグリタゾン塩酸塩
インスリンの効果を高め、肝臓で作られる糖を減らし、筋肉で糖の利用を増やすことで糖尿病の治療薬として使用されている薬です。
フランスの調査ではわずかながらこの薬を服用している人に膀胱がんの発生が多く見られたため、処方制限されることとなりました。その後アメリカで行われた調査ではピオグリタゾン塩酸塩を服用していた人は1年で10万人あたり8.2人が膀胱がんを発症、一般の人では6.9人だったことから、わずかに膀胱がんの発生が多いという結果になりました。
しかしこの薬は糖尿病治療薬としては優れた薬であり、現在日本では膀胱がんの人への投与は避けるように注意書きがなされていますが、糖尿病の治療薬として現在でも使用されています。
膀胱がんになりやすい人の特徴
膀胱がんは男性では45歳から、女性は50歳から発症者数が増えます。年齢が上がっても女性は比較的緩やかな増加ですが、男性では急激に増加します。60歳台前半を男女比で比較すると、男性の罹患は10万人あたり63.9人、女性は11.8人と約5.4倍の差があります。
死亡率についても男女比では最大5.6倍の差で男性のほうが多くなっています。
ヒトパピローマウイルスと膀胱がんの関連性
ヒトパピローマウイルス(HPV)は性感染症の1つで、性交渉のある人では高率に感染しています。
HPVの種類は200種類を超え、そのほとんどは感染しても無症状ですが、16型と18型のHPVはがんを引き起こします。女性における子宮頸がんの原因となっているウイルスですが、このウイルスが膀胱がんの発症にも関連しているのではないかと推測されています。
このウイルスは男性の外性器にも感染することが分かっていますが、尿道炎になっている男性患者の尿を検査したところ、正常の人では1.9%しか見られなかったHPVの感染が尿道炎の患者からは24%であったと報告されています。また摘出された膀胱がんの組織からHPVのDNAを調べた検査では15%が陽性であり、さらに発がん蛋白であるE7蛋白の陽性率を調べたところ、HPV陽性の組織では有意に多く発現を認めました。この調査は検討数が少なく、統計学的にHPVと膀胱がんの関連を証明することはできませんでしたが、HPV感染は膀胱がん発症の原因になっている可能性はあります。
予防と早期発見のコツ
膀胱がんの予防
喫煙は膀胱がんの危険因子ですが、10年以上禁煙すると、膀胱がんになる可能性はタバコを吸わない人と同じまで低下したと報告されています。ですから、膀胱がんの予防としてタバコを吸っている人には禁煙が勧められます。
そのほかにカフェインやミネラルウォーター、中国茶や個人輸入した漢方薬を服用している人は、その成分を調べ、必要に応じて摂取量を調整しましょう。
早期発見のためには
膀胱がんの初期症状として多いのは血尿です。尿の色は出血量や時間経過で異なりますが、赤や茶色、黒っぽい尿になることもあります。また、検診や人間ドックの尿検査で尿潜血が陽性だった場合には、膀胱がんを見逃さないようにきちんと精密検査を受けましょう。
そのほかにがんが膀胱を刺激して、頻尿や残尿感といった症状がでることもあります。このような症状は一般的には膀胱がんよりも膀胱炎を疑う症状ですが、適切な治療を受けても症状に改善が見られない場合は膀胱がんの可能性も疑いましょう。
蕗書房 | 膀胱がんの治療について
国立研究開発法人 国立がん研究センター | 喫煙と膀胱がんリスク
国立研究開発法人 国立がん研究センター | 喫煙、コーヒー、緑茶、カフェイン摂取と膀胱がん発生率との関係について
「芳香族アミン取扱事業場で発生した膀胱がんの 業務上外に関する検討会」報告書
東京蒲田病院泌尿器科 | 我が国における職業性膀胱癌の歴史と現状
日本内科学会雑誌 | 膠原病・リウマチ性疾患診療のより深い理解を目指して
株式会社ウチダ和漢薬 | ボウイ(防已) – 生薬の玉手箱
日本漢方協会 | 医薬品・医療用器等安全性情報に漢方生薬が載る
中央環境審議会大気環境部会 健康リスク総合専門委員会 | ヒ素及びその化合物に係る健康リスク評価について
飲料水と環境
医薬品・医療機器等安全性情報 | 糖尿病治療薬ピオグリタゾン塩酸塩含有製剤 による膀胱癌に係る安全対策について
チアゾリジン薬 | 糖尿病リソースガイド
がん登録・統計 グラフデータベース
国立がん研究センター | がん統計
男性の膀胱腫瘍の発症にHPVが関与、尿道炎患者の3割で高リスク型HPV検出【泌尿器科学会2011】
国立研究開発法人 国立がん研究センター | 喫煙、コーヒー、緑茶、カフェイン摂取と膀胱がん発生率との関係について
MSDマニュアル プロフェッショナル版 | 泌尿器疾患
MSD oncology がんを生きる | 膀胱とは | 膀胱がんとは
国立がん研究センター がん情報サービス | 膀胱がん
参照日:2020年9月